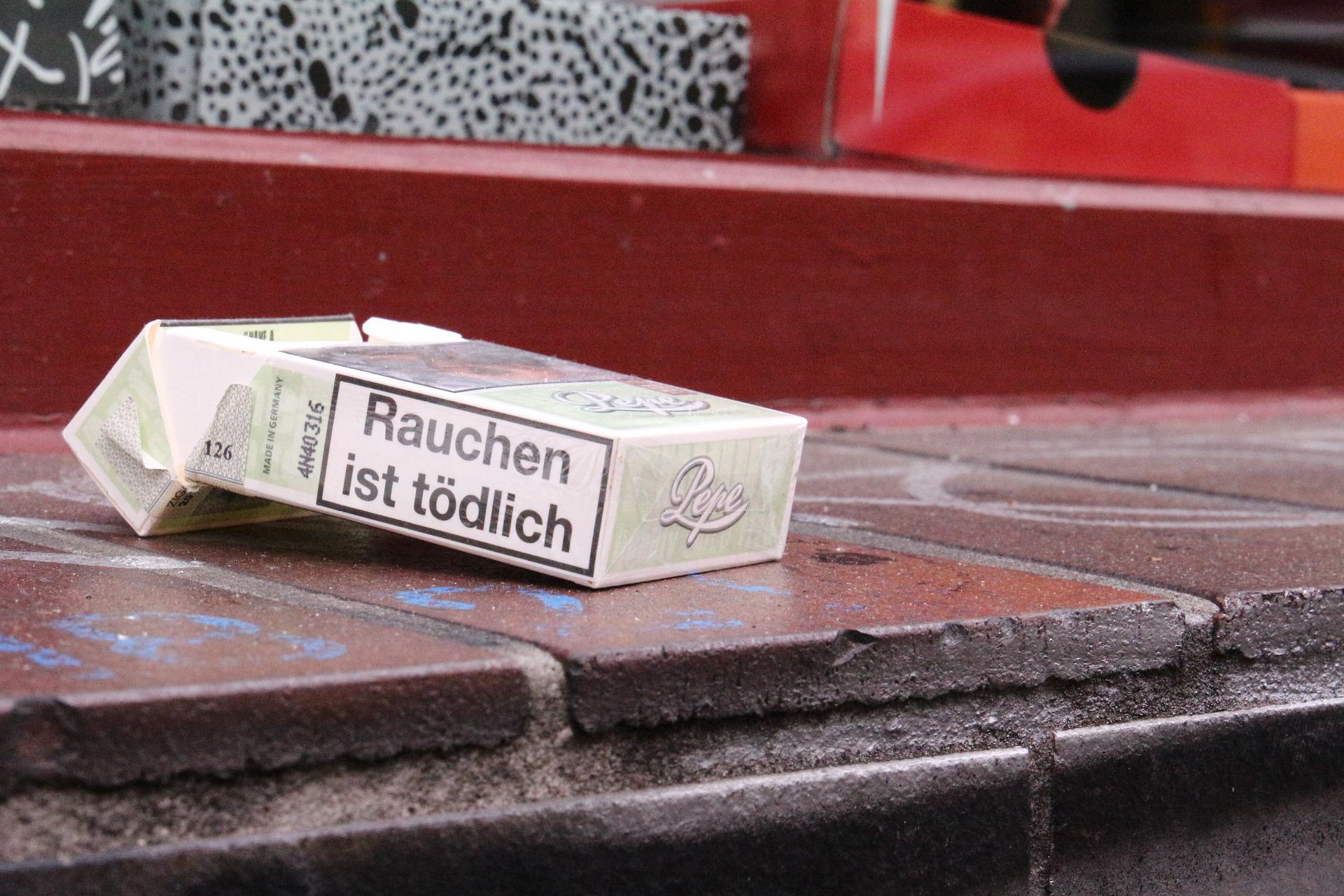2025.03.03
喫煙所コラム
喫煙の自由は認められるのか?判例はどうなっている?

喫煙者にとっては、厳しい環境となっていますが、喫煙者の中には「喫煙の自由」を主張する人もいるでしょう。
今回のコラムでは、「喫煙の自由は認められるのか?」「判例はどうなっているのか?」について解説します。
喫煙をする権利はあるが制限もある
日本では、喫煙に関する法律も改正され、喫煙者にとっては厳しい環境となっています。
時代の流れだから仕方がないと考えている人もいるでしょうが、「喫煙の自由は認められないのか?」と疑問に感じている人もいることでしょう。
そこで気になるのが、判例ではどうなっているのか、ということです。
● 愛煙家だった原告が未決拘留中、刑務所で喫煙を希望したものの刑務所での喫煙を拒否されたことにより、苦役を強制されたとして国家賠償を求めた裁判。
この裁判は、特殊な状況ですが、次のような判決が出ています。
監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。
他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。
(出典:最高裁判所判例集)
喫煙の自由に関する判例を見ると、権利については認められるが、無条件・無制限で喫煙が可能という意味ではなく、状況によっては制限されることもあると解釈することができます。
喫煙者の方は、この点についてしっかりと理解しておきましょう。
喫煙については法律や条例、マナーを守ることが重要
喫煙の自由については、常に認められるということではなく、制限されることもあると解説しました。
では、喫煙者が喫煙をするためには、どうすればよいのでしょうか?
現在の法律では、受動喫煙防止がルール化されています。
そのため、喫煙をする場合には、法律はもちろんですが、各自治体の条例、喫煙に関するマナーを守らなければなりません。
とくに、法律については施設の種類によっても異なりますので、それぞれの施設のルールに従うことが大切です。
従わない場合には、処罰されることもあるため、正しいルールをしっかりと理解しておきましょう。
喫煙マナーとして覚えておきたいのが、次のようなものです。
● 喫煙は許可された場所のみで行い、禁止された場所での喫煙はしない
各自治体では、路上喫煙禁止区域などが設定されている場合もありますので、各自治体のホームページ等でもしっかりと確認しておきましょう。
● 歩きたばこの禁止
歩きたばこは非常に危険な行為であり、他の人に危険を及ぼす可能性があります。
とくに、小さな子どもなどが歩きたばこによって、やけど等をしてしまう可能性があるため、絶対にやめましょう。
取り返しのつかない事態にもなりかねません。
● 自宅のベランダや庭での喫煙も避ける
受動喫煙防止がルール化されていますが、自宅であればベランダでも庭でも自由に喫煙ができると考えていませんか?
大きな問題となっているのが、ベランダで喫煙をして周囲とトラブルになるというものです。
たばこの煙は、風に乗って周囲の部屋にも届いてしまいますので、臭いなどで大きなトラブルとなる場合があります。
トラブルになると、周囲との関係が悪化してしまい、住みづらくなってしまうことでしょう。
状況によっては、引越し等を検討しなければならなくなります。
● 吸い殻のポイ捨て禁止
こちらも大きな問題となっているのが、吸い殻のポイ捨てです。
吸い殻のポイ捨てを行うと、過料が科せられる場合もあるため、ポイ捨ては絶対にやめましょう。
また、過料が科せられるだけでなく、火がついたままの吸い殻をポイ捨てすると、火災の原因にもなります。
火災が発生した場合には、他の人に大きな迷惑をかけることになりますし、最悪の場合には他の人の命を奪ってしまう恐れもあるのです。
● 子どもや妊婦の近くでの喫煙はしない
それから、必ず覚えておかなければいけないのが、子どもや妊婦の近くでの喫煙はしないということ。
この理由は、ご存知の方も多いと思いますが、健康への影響が大きいと考えられるためです。
具体的には、早産や低体重児の出産、SIDS等のリスクを高める可能性があるため、リスクを小さくするためにも注意しましょう。
たばこの煙には、多くの有害物質等が含まれているため、十分な注意が必要となります。
配慮義務は喫煙者だけでなく施設管理者にもある
皆さんは配慮義務というものをご存知でしょうか?
(喫煙をする際の配慮義務等)
第27条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等(以下この章において「特定施設等」という。)の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。
2 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。
(出典:健康増進法)
配慮義務と聞くと、喫煙者だけに生じるものと誤った認識をしている人もいるようですが、施設管理者についても配慮義務が生じているのです。
配慮に関しての具体的な規定はありませんが、一般的には施設管理者の配慮義務の例として、次のようなものがあります。
● 人通りの多い場所に灰皿を設置しない
● パーテーションを設置して、たばこの煙が周囲に流れないように工夫をする
● 営業時間外には灰皿を片付ける
● 定期的に掃除を行う
● 喫煙者が密集しすぎないように注意する
あくまでも上記のものは一例ですが、施設管理者は例を参考にして対応をするようにしましょう。
喫煙者と非喫煙者が共存するためには、喫煙の自由を主張するのではなく、喫煙に関するルールやマナーを守り、両者を尊重することが非常に重要となります。
▼導入実績はコチラから
施設別導入事例
まとめ
喫煙者にとっては厳しい環境となり、喫煙の自由は認められるのか、が気になるところですが、判例を見てみると、喫煙をする権利は認められているが、状況によっては制限されるということです。
大切なことは、法律や条例、マナーなどを守り、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築することと言えるでしょう。