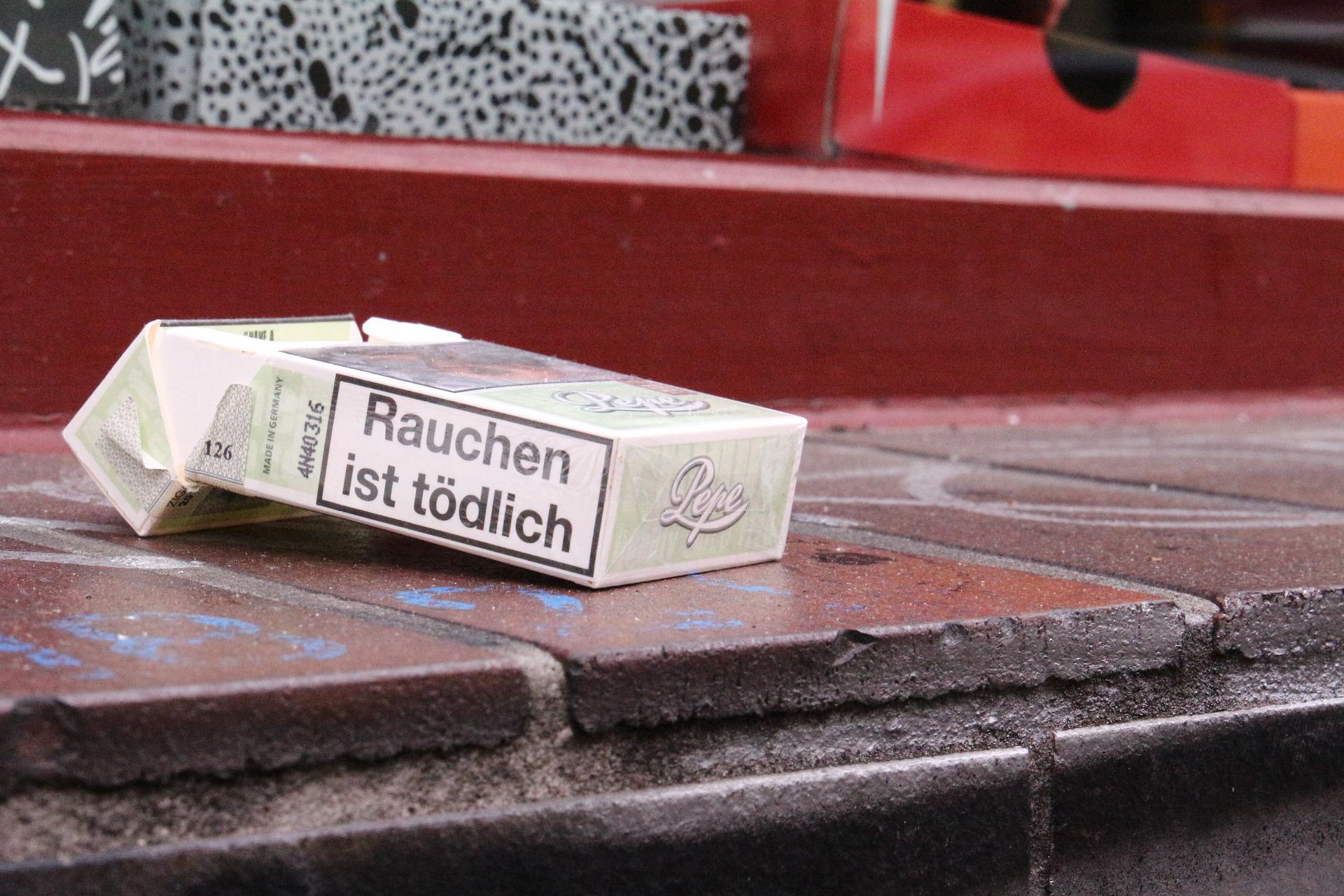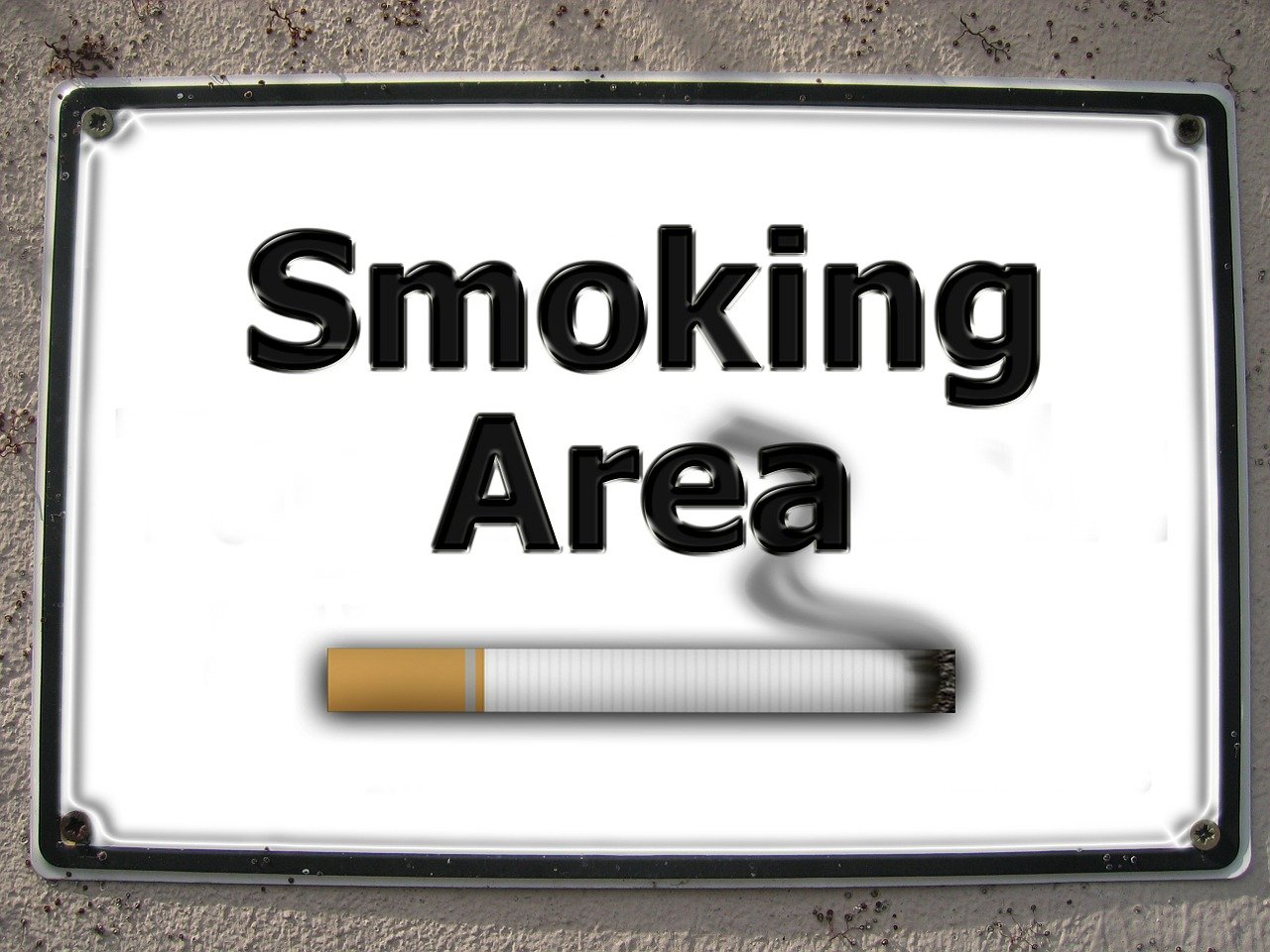2023.05.15
喫煙所コラム
改正健康増進法のポイントや違反した場合の罰則について

喫煙に関する法律として、押さえておかなければいけないのが「改正健康増進法」です。
今回のコラムでは、改正健康増進法のポイントや違反した場合の罰則について詳しく解説します。
喫煙者だけでなく、施設の管理者もしっかりと理解しておきましょう。
改正健康増進法とは?
改正健康増進法のポイントや違反した場合の罰則について、解説する前に理解しておきたいのが、「改正健康増進法とは?」です。
日本では、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立して、2020年4月に全面施行されていますが、これが改正健康増進法と呼ばれるものになります。
では、どうして健康増進法の一部が改正されたのか、についてですが改正の趣旨として、基本的考え方が3つ示されているのです。
① 望まない受動喫煙をなくす
② 受動喫煙による健康への影響が大きいと考えられる子どもや患者等に特に配慮する
③ 施設の類型や場所にあわせて対策を行うこと
改正健康増進法のポイント
次に知っておきたいのが、改正健康増進法のポイントについてです。
具体的に、どのような点が健康増進法と変わったのか、を押さえておかなければなりません。
改正健康増進法の大きなポイントは、「望まない受動喫煙」を防止するための対策がマナーからルールに変わったことです。
マナーからルールに変わったと解説しましたが、もう少し具体的に改正健康増進法のポイントについて見ていきましょう。
多くの施設で屋内が原則禁煙となった
大きなポイントとしては、多くの施設で屋内が原則禁煙となった点です。
これまでは、屋内での喫煙も可能でしたが、改正健康増進法では原則禁煙となっています。
ただし、一定の条件をクリアすることで、喫煙室を設置できる場合もありますが、施設の種類によっては、屋内だけでなく敷地内禁煙となっている場合もあるのが大きなポイントです。
20歳未満は従業員であっても喫煙エリアに入ることができない
さらに、押さえておきたいポイントは、20歳未満については喫煙エリアに入ることができないということ。
施設の利用者だけでなく、従業員にも適用されています。
ですから、喫煙室の灰皿の清掃などで立ち入ることもできません。
法律では、喫煙以外の目的であっても立ち入ることは認められていませんので、注意が必要です。
この点を正しく理解しておらず、20歳未満の従業員等を喫煙可能なエリアに立ち入らせた場合には、指導や助言の対象となるため管理者はしっかりと押さえておきましょう。
喫煙室等を設置する場合には標識の提示が必要
それから、喫煙室等を設置する場合には、必ず標識の掲示が義務付けられている点も重要なポイントです。
標識はただ掲示すればよいというものではなく、紛らわしいものや汚損等は禁止で、そのようなものを掲示している場合には罰則の対象となる場合があります。
また、標識の掲示については、設置する喫煙室(設備)にあわせて、最適なものを掲示しなければなりません。
この場合の喫煙室とは、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室・喫煙目的室・喫煙可能室などです。
施設によって設置可能な喫煙室が異なる
施設の種類によっては、屋内に喫煙室を設置することができます。
しかし、喫煙室にもいくつかの種類のものがあり、施設によって設置可能なものとそうでないものがあるのです。
【喫煙専用室】
喫煙専用室とは、名称からも想像することができますが、喫煙が可能な喫煙室ですが、飲食等はできません。
施設の一部に設置することができます。
【加熱式たばこ専用喫煙室】
加熱式たばこ専用喫煙室は、喫煙ができるという点で、喫煙専用室と似ていますが、喫煙が認められているのは、加熱式たばこのみという点が大きな違いです。
それから、もう1つ喫煙専用室と大きく異なる点があります。
その大きく異なる点とは、飲食等が可能であることです。
また、こちらも施設の一部に設置が可能となっています。
【喫煙目的室】
喫煙目的室とは、喫煙が可能なだけでなく、主食を除く飲食等が可能となっているのが大きな特徴です。
こちらについては、施設の全部もしくは一部に設置することができます。
ただし、喫煙目的室を設置できる施設については、喫煙目的施設に限定されているのです。
それ以外の施設には設置ができない点に注意が必要となります。
【喫煙可能室】
喫煙可能室については、喫煙と飲食等が可能です。
施設の全部もしくは一部に設置することができます。
ですが、こちらについても設置できる施設は限定されており、既存特定飲食提供施設のみです。
ここでは、4つの喫煙室について解説しましたが、どの喫煙室を設置してもよいというものではなく、施設によって設置できるものと設置できないものがあるということを理解しておきましょう。
一般的な施設においては、喫煙専用室もしくは加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。
屋内に喫煙室等を設置する場合には技術的基準をクリアしなければならない
多くの施設では、原則屋内禁煙となっていますが、施設の種類によっては屋内に喫煙室等を設置することが可能です。
ただし、自由に設置ができるという意味ではありません。
屋内に設置するには、技術的基準をクリアする必要があります。
この技術的基準をクリアしなければ、設置することができないのはもちろんですが、違反となってしまう点にも注意が必要です。
それから、同時に押さえておきたいのが、屋内ではなく屋外について。
学校や病院等の第一種施設においては、敷地内禁煙となっているため、屋内に喫煙室を設置することはできません。
ですが、屋外に特定屋外喫煙場所を設置することができます。
この特定屋外喫煙場所とは、以下のような措置がとられている場所のことです。
・喫煙可能な場所と喫煙禁止場所が区画されていること
・喫煙可能な場所であることを標識によって掲示していること
・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する(建物の裏や屋上等)
また、第一種施設については、すでに解説しているように屋外も規制の対象となっていますが、第二種施設については、屋外は規制の対象外となっているのです。
規制の対象外であると聞くと、喫煙が自由というイメージがあるでしょうが、規制の対象外でも配慮義務があります。
この配慮義務を怠ると、非喫煙者と喫煙をめぐり大きなトラブルとなる場合がありますし、最悪の場合には訴訟等に発展してしまう可能性もあるのです。
そのため、配慮義務を怠らないことが重要となります。
違反した場合には罰則が適用される
改正健康増進法で、必ず押さえておかなければいけないのが、違反した場合には罰則が適用されるということ。
違反した場合には、指導・助言・勧告・公表・命令・過料などになります。
過料については、違反した内容によっても異なりますが、最大で50万円以下の過料となる場合もあるのです。
改正健康増進法における義務について
改正健康増進法では、義務対象や義務の内容についても正しく理解しておかなければなりません。
理解しておかなければならない義務対象と義務の内容については、以下のようなものがあります。
【義務対象 全ての者】
(義務の内容)
・喫煙禁止場所における喫煙禁止
・紛らわしい標識の掲示を禁止また標識の汚損等の禁止
【施設等の管理権原者】
(義務の内容)
・喫煙器具や設備などの撤去等
・施設標識の掲示・除去
・喫煙室の基準適合
・従業員を含む20歳未満の者への喫煙エリアへの立入禁止
・書類の保存
・立入検査への対応
・広告・宣伝
(参考:改正法のポイント)
このように、義務の対象や内容については、しっかりと理解しておかないと、罰則が適用される場合があります。
屋内に喫煙専用室を設置する場合には基準に注意
施設の種類によっては、屋内に喫煙専用室等を設置することもできますが、どのようなものでも作れるということではありません。
設置する場合には、一定の技術的基準をクリアしなければならないのです。
この技術的基準とは、次のようなものになります。
・出入口における室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上となっていること
・たばこの煙が屋外もしくは外部に排気されていること
・たばこの煙の流出を防ぐために、壁や天井などで区画されていること
以上のような条件をクリアしていなければ、設置することはできない決まりとなっています。
もしも、技術的基準をクリアしていない喫煙専用室等を設置した場合には、施設等の管理権原者に50万円以下の過料が科せられる可能性があるのです。
ですから、屋内に喫煙専用室等を設置する場合には、技術的基準をしっかりとクリアしているかを確認しておきましょう。
屋内に喫煙室を設置する場合には、専門の業者に依頼することになりますが、業者を選ぶ際には、法律について正しく理解しており、実績が豊富な業者を選ぶのがよいでしょう。
価格だけで選んでしまうと、法律を正しく理解していない、基準をクリアした喫煙室を設置できない、などの問題が起こるリスクが高まります。
このようなリスクをできるだけ小さくするためにも、業者選びも慎重に行うようにしましょう。
弊社では、屋内もしくは屋外の喫煙室を豊富にご用意しております。
納入実績も豊富で、さまざまな場所に喫煙室を設置しておりますので、お気軽にご相談ください。
法律を守り、それぞれにあわせて最適なご提案をいたします。
▼製品一覧はコチラから
屋外喫煙所一覧
まとめ
改正健康増進法は、健康増進法の一部を改正した法律のことです。
大きなポイントは、これまでは望まない受動喫煙を防止するというのがマナーだったものが、法律の改正によってルール化されたこと。
さらに、必ず覚えておかなければいけないのが、違反した場合には罰則があるということです。
違反した内容によって異なりますが、最大で50万円以下の過料となる場合があるため、十分注意しなければなりません。