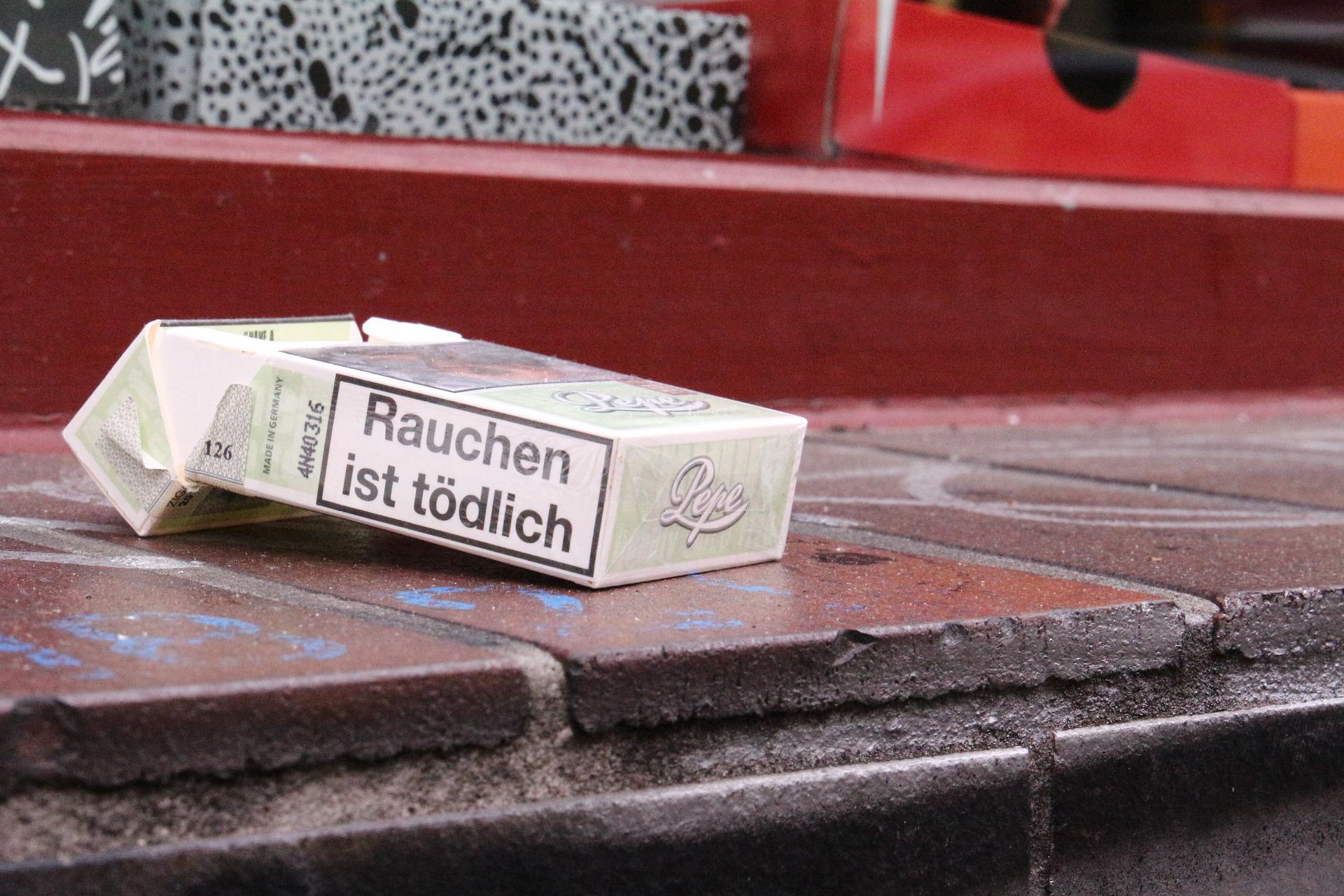2025.03.03
喫煙所コラム
喫煙者差別とはどのようなもの?具体的な事例とは?

皆さんは、「喫煙者差別」という言葉を聞いたことがありますか?
喫煙者にとっては、厳しい環境になっているため、実際に体験したという喫煙者もいるかもしれません。
今回のコラムでは、「喫煙者差別とはどのようなものなのか?」「具体的な事例とは?」について解説します。
喫煙者差別とは喫煙をしていることを理由に不当な扱いを受けること
日本では、喫煙に関する法律も改正され、喫煙者にとっては非常に厳しい環境となっています。
そこで、注意しておきたいのが「喫煙者差別」についてです。
この言葉を耳にしたことがある、新聞や雑誌などで目にしたことがあるという人もいるかもしれません。
一般的に、喫煙者差別とは、喫煙していることを理由に不当な扱いを受けてしまうことです。
具体的な事例としては、次のようなものがあります。
● 喫煙を理由に不採用とされる
現在では、喫煙者は採用しないという方針の企業も増えており、非喫煙者よりも喫煙者は採用されるのが難しいケースがあるようです。
また、喫煙者を採用しない企業の採用しない主な理由としては、次のようなものが挙げられています。
・ 作業効率
・ 施設効率
・ 職場環境
喫煙者の場合、血液中のニコチン含有量が減少することで、集中力の維持が難しくなり、作業効率の低下につながると考えられているようです。
また、現在の法律では受動喫煙防止がルール化されており、分煙環境を整えるためには、喫煙可能スペースを設置しなければならず、そこへの投資が利益を圧迫する可能性があるとも考えられています。
それから、いわゆるたばこ休憩のように、喫煙者だけが頻繁に休憩が認められてしまうことは、非喫煙者からすると、不公平と感じてしまうなど職場環境に悪影響を及ぼす可能性があるとも考えられているようです。
● 喫煙が理由で避けられる
採用の場面以外では、喫煙をしていることを理由に、低評価とされてしまうケースや避けられてしまう場合もあります。
上司や同僚から評価されない、または避けられてしまうというのは、喫煙者にとって非常につらい状況です。
ただし、非喫煙者がすべて悪いとは言い切れません。
非喫煙者の中には、たばこの臭いが苦手な人や不快と感じている人も多いため、喫煙者の服などから臭うたばこの煙を嫌がっているために、避けられてしまっていることがあります。
また、たばこの影響によって口臭がきつくなる場合もあり、近づくのを避けられてしまう場合もあるようです。
たばこには、有害物質などが多く含まれているため、それらの影響によって、嫌な臭いが発生してしまいます。
臭いの問題を解決することで、周囲との関係を改善できる可能性がありますが、そのまま放置していると、関係を改善するのが難しくなってしまうでしょう。
喫煙を理由に不採用となるのは差別や違法となるのか?
喫煙者差別の事例の1つとして、喫煙を理由に不採用となる、というのを紹介しました。
ここで考えておきたいのが、喫煙を理由に不採用とするのは、差別や違法となるのか、についてです。
結論から言えば、差別や違法にはならないということになります。
日本には、喫煙を理由として採用しないことを禁止している法律はありません。
そのため、企業が喫煙者を採用しないとしていても、差別や違法にはあたらないと考えられています。
企業には採用の自由が認められているため、喫煙者を採用しないという採用活動も法的には問題がないと考えられているのです。
採用の自由が認められていると解説しましたが、どのような採用活動も認められるということではありません。
次のようなものは禁止されています。
● 年齢制限の禁止
喫煙を理由に不採用とすることは可能ですが、募集や採用で年齢を理由に不採用とすることはできないことになるのです。
例外的に年齢制限を設ける場合には、その理由を提示しなければならない決まりとなっています。
改正雇用対策法第10条には、以下のように書かれているのです。
第10条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(出典:雇用対策法の改正について)
また、性別を理由とする差別や募集・採用は違法となっています。
男女雇用機会均等法には、以下のように書かれているのです。
(性別を理由とする差別の禁止)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
(性別以外の事由を要件とする措置)
第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
(出典:男女雇用機会均等法)
第5条では性別による直接差別を禁止しており、第7条では間接差別を禁止しています。
もう少し詳しく解説すると、性別を理由とする差別とは、募集をする際に男女のいずかを排除してしまう、採用条件を男女で異なるものにしてしまう、男女のいずれかを優遇もしくは優先してしまうことなどです。
性別を理由とする差別は、違法となるため十分な注意が必要となります。
間接差別とは、合理的な理由がないのに、身長・体重・体力などを要件とすることや転居を伴う転勤に応じることを要件とすることなどです。
こちらも合理的な理由がない場合には、違法となるため注意が必要となります。
(参考:男女均等な採用選考ルール)
差別ではなく共存できる環境を整えることが必要
喫煙者にとっては非常に厳しい環境となっていますが、喫煙をしていることを理由に差別されてしまうのは、よいこととは言えません。
大切なことは差別をすることではなく、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を整えることです。
一般企業の中には、喫煙者と非喫煙者が混在しているケースが多くなっています。
喫煙者だけに制限を設けるのではなく、分煙環境を整備して、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を整えるのがよいでしょう。
分煙環境を整えるには、法律に基づいたものを設置する必要がありますし、施設の種類によっても法律が異なりますので、専門的な知識を持つ業者に相談するのがおすすめです。
弊社では、分煙コンサルタントを配置しておりますので、分煙に関するご相談を受け付けております。
また、屋内や屋外に設置できる喫煙所を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
▼導入実績はコチラから
施設別導入事例
まとめ
喫煙していることを理由に、不採用となってしまうケースや上司・同僚からの評価が低くなってしまう場合があります。
ただし、採用については差別や違法になるとは言えません。
一般的な企業では、喫煙者と非喫煙者が混在していますので、差別ではなく両者が共存できる環境を整えることが重要となります。
弊社では、分煙コンサルタントを配置しておりますので、お気軽にご相談ください。