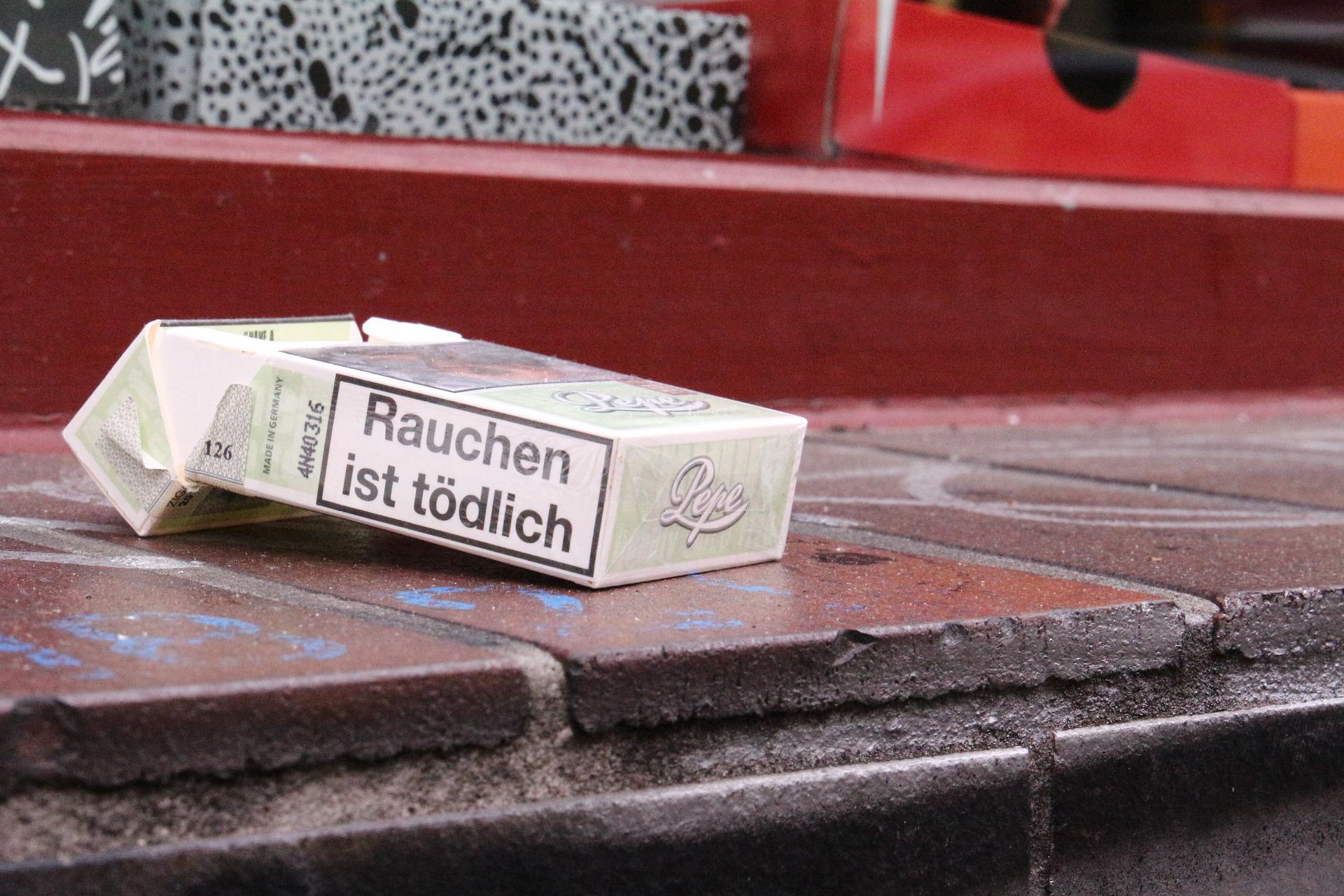2025.09.09
喫煙所コラム
企業が敷地内全面禁煙を実施するのはどのような理由から?

国内企業の一部では、敷地内全面禁煙を実施しています。
では、どうして「敷地内全面禁煙」を実施する企業が出てきているのでしょうか?
今回のコラムでは、実施する主な理由について解説します。
従業員の健康維持や増進を目的として実施している
国内企業の一部では、敷地内全面禁煙を実施しているところがあります。
一般的なオフィス・事務所などでは、「原則屋内禁煙」がルールとなっていますが、どうして「敷地内全面禁煙」を実施する企業があるのでしょうか?
実施する主な理由としては、次のようなものがあります。
従業員の健康維持や増進のため
企業が敷地内全面禁煙を実施する主な理由としては、「従業員の健康維持や増進のため」というものがあります。
企業が成長していくためには、その企業で働く従業員はもちろん、その家族の健康が非常に重要であるという考えから、敷地内全面禁煙を実施しているのです。
受動喫煙のリスクを小さくするため
それから、もう1つ大きな理由として挙げられるのが、受動喫煙のリスクを小さくするためというもの。
企業によっては、法律に基づいて屋内もしくは屋外等に、喫煙可能なスペースを設けている場合があります。
喫煙者にとっては、非常に快適に過ごすことができますが、設置場所などによっては、受動喫煙のリスクがあるため、非喫煙者にとっては、快適な環境とは言えません。
ですが、敷地内全面禁煙を実施すれば、喫煙ができなくなるため、受動喫煙のリスクが小さくなり、非喫煙者や子どもなども安心して過ごすことができる環境となるのです。
国内では健康経営に取り組む企業が増えている
最初に、どのような理由から、企業が敷地内全面禁煙を実施しているのか、について解説しました。
次に知っておきたいのが、「国内では健康経営に取り組む企業が増えている」ということです。
ここで気になるのが、「健康経営」という言葉。
経済産業省のホームページでは、健康経営について、以下のように解説されています。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。
健康経営は、日本再興戦略、未来投資戦略に位置づけられた「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みの一つです。
(出典:経済産業省 健康経営)
また、健康経営優良法人認定制度があり、健康経営に取り組んでいる優良な企業が可視化されています。
可視化することによって、取引先・顧客・金融機関などから、社会的に高い評価を受けることも期待できるでしょう。
健康経営の具体的な取り組みについて
健康経営優良法人認定制度があること、認定されることで、社会的に高い評価を受けられる可能性があること、などを解説しました。
では、健康経営とは、具体的にどのようなことを行っているのでしょうか?
敷地内全面禁煙だけでなく、その他にもさまざまな取り組みが行われています。
就業時間内禁煙(休憩時間を除く)
取り組みの中でもよく知られているのが、就業時間内禁煙です。
こちらは、文字通りの意味で、就業時間中は禁煙を行うというものになります。
就業時間内禁煙を行うのは、受動喫煙を防止すること、従業員の健康維持や増進のためです。
それから、生産性の向上にも期待することができるでしょう。
さらに、複数の社員が共有するもの、例えば社用車についても禁煙としている企業があります。
社用車については、特定の社員が使用するというものではなく、複数の社員が使用する可能性があるため、禁煙としているケースがあるのです。
社用車については、禁煙のステッカーを貼り付けるなどして、誤って喫煙をしないようにしています。
禁煙サポート
また、従業員を対象とした禁煙サポートも行われています。
サポート内容は、それぞれの企業によって異なりますが、一般的には、禁煙にかかる費用の負担や補助などです。
さらに、産業医による禁煙指導やオンラインを活用した禁煙プログラムなどを提供している場合もあります。
従業員だけでは、金銭面や精神面などから、禁煙を行うのが難しい場合が多いですが、さまざまなサポートを行うことで、従業員の禁煙を後押ししているのです。
手当の支給
さきほどは、禁煙サポートについて紹介しましたが、行われているのはサポートだけではありません。
その他では、手当の支給を行っている企業もあります。
手当としては、非喫煙者に対して手当を支給するというものや喫煙をしていたけれど、卒煙をした人を対象に支給するというものなどです。
社内だけでなく社外にも自社の取り組み内容を発信
その他では、情報の発信があります。
この情報とは、自社が禁煙あるいは卒煙に取り組んでいる内容についての情報です。
社内だけでなく、外部の人にどのような取り組みを行っているのか、について理解してもらうことが難しいですが、社外にも自社の取り組み内容を発信することで、取り組みを多くの人に知ってもらうことができます。
敷地内全面禁煙を実施する場合の問題点について
企業では、すでに解説しているように、従業員の健康維持や増進のため、受動喫煙を防止するために「敷地内全面禁煙」を実施する企業が増えているようです。
たしかに、その理由を聞くと納得できる人も多いと思いますが、本当に問題はないのでしょうか?
結論から言えば、いくつかの問題があると言えます。
具体的な問題としては、次のような問題です。
喫煙者の不満がたまりやすくなる
まず、大きな問題と言えるのが、喫煙者の不満がたまりやすくなること。
たしかに、健康面や受動喫煙のリスクを考慮すれば、企業が敷地内全面禁煙を実施するのも仕方ないかもしれません。
しかし、喫煙者だけが我慢しなければならないとなると、どうしても喫煙者の不満がたまってしまうことがあります。
新たな問題が発生するリスク
それから、次に問題として挙げられるのが、新たな問題が発生するリスクについてです。
例えば、次のようなケース。
これまでは、屋内もしくは屋外に喫煙スペースを設けていたものの、敷地内全面禁煙を実施するために、喫煙スペースをすべて撤去してしまったというケースです。
喫煙スペースが設置されていたときは、そこで喫煙をすることができたため、大きな問題は出なかったかもしれません。
ですが、これまで喫煙していた場所がなくなってしまったとしたら、喫煙者はどのような行動に出るでしょうか?
実際に起こっているのが、敷地外にある近くの喫煙所を利用するというケースです。
敷地内で喫煙ができなくなってしまったため、喫煙が可能な近くの喫煙所に移動して利用してしまうというもの。
もちろん、1人や2人などであれば、大きな問題にはならないかもしれません。
しかし、多くの従業員が一斉に利用してしまったらどうなるでしょうか?
たばこの吸い殻の問題・臭いの問題などが新しく発生してしまう可能性があります。
また、問題が発生するというだけでなく、近隣住民との関係が悪化してしまう可能性もあるのです。
近隣住民との関係が悪化してしまうと、事業を継続するのが困難となってしまうケースもあるでしょう。
さらに、関係が悪化してしまうと、社会的な面でも評価を落としてしまうことになりかねません。
クレームの増加
新たな問題が発生するリスクについて解説しましたが、そのリスクの中には、クレームが増加してしまうリスクもあります。
「おたくの従業員が喫煙をしていて煙がすごい!」「吸い殻をポイ捨てしている!」などのクレームが近隣住民から寄せられてしまう可能性があるのです。
敷地内全面禁煙を実施することで、喫煙できない従業員が我慢できずに、隠れて喫煙してしまうケースや近隣の施設で喫煙をしてしまうなどの場合。
このようなクレームを受けてしまうと、企業として対応しなければならなくなるでしょう。
近隣住民からのクレームに対応しようとすると、人も時間もかかりますので、本来の業務にも影響が出てしまうおそれがあります。
クレームの数が多くなると、従業員が対応を嫌がる、精神的な面で大きなダメージを受けてしまうなどが考えられるでしょう。
敷地内全面禁煙を行うために必要なことは理解を得ること
企業が敷地内全面禁煙を実施する場合、さまざまな問題が発生するリスクがあると解説しました。
では、このようなリスクをできるだけ小さくするためには、何ができるのか、について考えてみましょう。
できることとして挙げられるのは、次のようなものになります。
喫煙者に理解を求める
一般的な企業では、喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
ですから、喫煙者だけに我慢を求めて、敷地内全面禁煙を実施するというのは、よいやり方とは言えません。
実施をする前に、喫煙者に対して理解を求めることが何よりも重要となります。
喫煙者に対して、どのような目的で実施するのか、どのような効果を求めているのか、などをきちんと説明して、喫煙者に理解してもらう必要があります。
何の説明もせずに、経営陣だけが勝手に決めてしまうと、喫煙者の不満がたまることになりかねません。
喫煙者に理解を求めて、できるだけ納得した形で、実施するのがよいでしょう。
段階的に進める
喫煙スペースを設けている企業が、いきなりすべての喫煙スペースを撤去して、敷地内全面禁煙を実施するとなると、喫煙者は大きく混乱してしまいますし、大きな反発を受けるおそれがあります。
そのため、いきなりすべての喫煙スペースをなくすのではなく、段階的に進めるのがよいでしょう。
例えば、喫煙スペースが4か所あるという場合には、まずは喫煙スペースを2か所に集約して、その後に敷地内全面禁煙を実施するという方法です。
段階的に進めることによって、喫煙者の混乱を避けることができますし、喫煙者にも納得してもらいやすくなると考えられます。
従業員に教育を行う
その他で重要となるのが、従業員に対して教育を行うことです。
この場合の教育とは、業務に関する教育のことではなく、喫煙に関する教育になります。
具体的には、「喫煙をすることでどのようなリスクがあるのか?(健康面のリスクなど)」「禁煙することでどのようなメリットがあるのか?」などについての教育です。
喫煙が習慣化されてしまっていると、喫煙のリスクや禁煙を行った場合のメリットについて考える機会は少ないと考えられます。
ですから、従業員に教育を行うことで、喫煙を続けるリスクや禁煙することのメリットについて正しく理解してもらうことができるのです。
教育をしっかりと行うことで、敷地内全面禁煙を受け入れてもらえる可能性が高まると考えられます。
また、教育を行う場合の重要なポイントとして挙げておきたいのが、喫煙は喫煙者だけでなく、周囲の人にも主に健康面で迷惑をかけてしまう場合があるということです。
その他にも、子どもへの影響が大きいということも教育の中に入れておきましょう。
喫煙スペースの場所の見直し
現在、喫煙スペースを設置している企業の中には、喫煙スペースに関する問題が多いため、敷地内全面禁煙を実施するというケースもあると思います。
例えば、屋内に法律に基づいた喫煙スペースを設置している場合。
このような場合は、設置場所が屋内であるという点から、煙や臭いが流れてしまうなどの問題が起こりやすくなります。
問題を放置してしまうと、さらに大きな問題として発展してしまう可能性がありますが、喫煙スペースの設置場所を変更するだけでも、状況を改善できる場合があるのです。
よくあるのが、喫煙スペースを屋内から屋外に移動させるというもの。
屋外で通常施設利用者が立ち入らないような場所であれば、これまでの悪い状況を改善できる可能性があります。
全面禁煙とする前に、現在の喫煙スペースの設置場所は適切なのか、について確認しておきましょう。
▼導入実績はコチラから
施設別導入事例
まとめ
企業が敷地内全面禁煙を実施するのは、従業員の健康維持や増進のため、受動喫煙のリスクを抑えるためです。
また、健康経営優良法人認定制度があり、健康経営に取り組んでいる優良な企業が可視化されています。
いきなり、敷地内全面禁煙を実施するとなると、喫煙者からの大きな反発が予想されるため、
できるだけ理解してもらえるように理解を求めることが大切です。