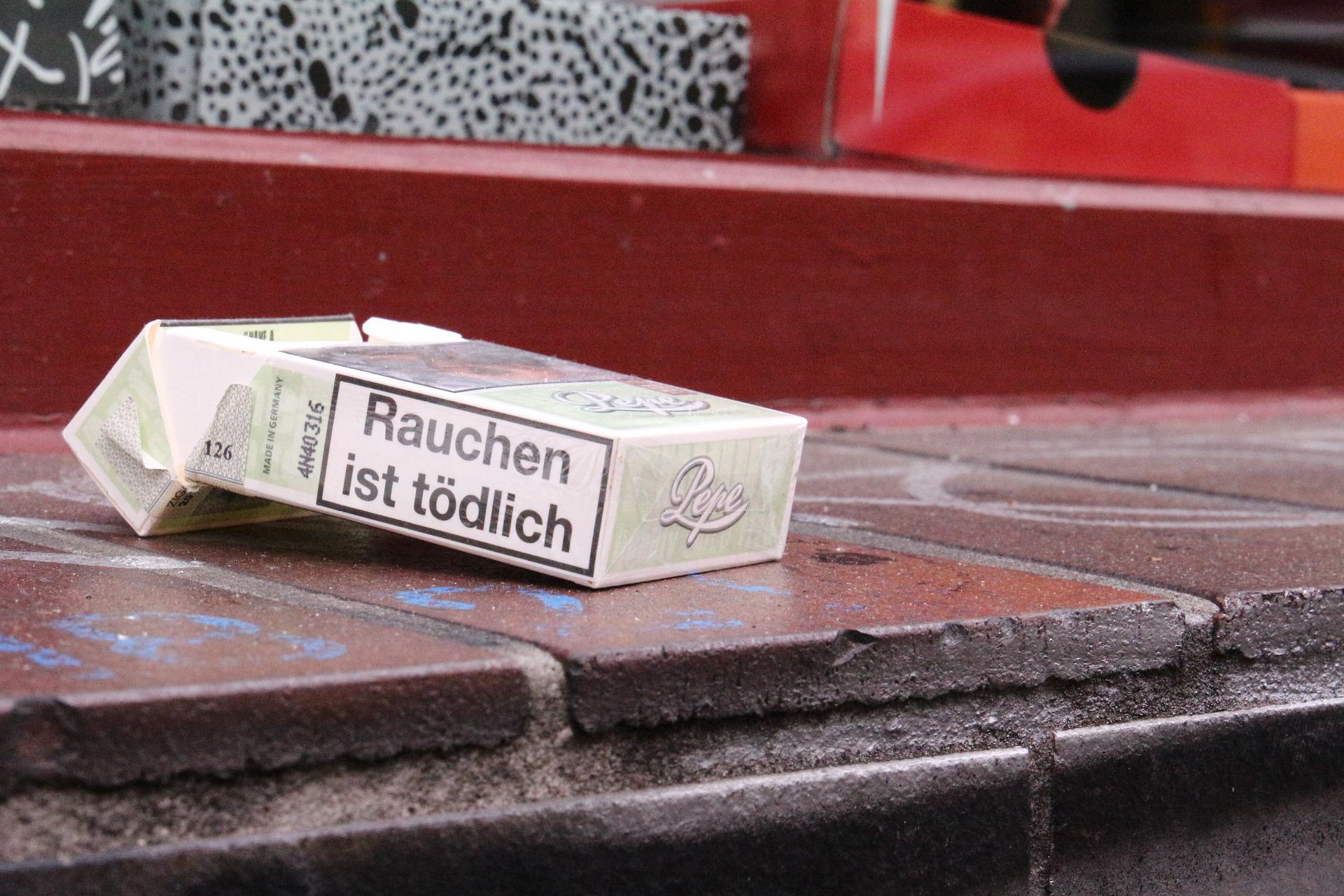2025.10.07
喫煙所コラム
主流煙と副流煙ではどっちが悪い?健康への影響は?
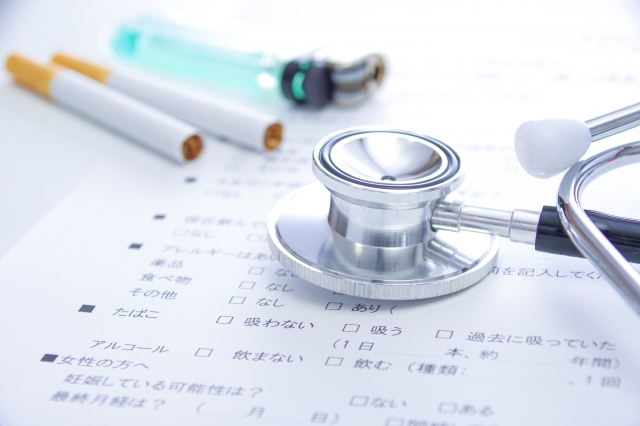
喫煙でよく聞かれるのが、「主流煙」と「副流煙」という言葉です。
皆さんは、この2つの違いについて知っていますか?
今回のコラムでは、「主流煙」と「副流煙」のどっちが悪いのか、健康への影響はどのようなものなのか、について解説します。
タバコの煙には「主流煙」や「副流煙」がある
タバコの煙でよく聞かれるのが、「主流煙」と「副流煙」という言葉です。
どちらもタバコの煙には、間違いないのですが、違いがあります。
まず、主流煙についてですが、こちらは喫煙をする際に、喫煙者が吸いこむタバコの煙のことです。
一方の副流煙とは、火のついているタバコの先端から立ち上る煙のことを言います。
この主流煙と副流煙は、ともに有害物質を含んでいますが、含有量が違うのです。
おそらく多くの人のイメージとしては、喫煙者が吸いこむ、主流煙の方が多くの有害物質を含んでいると思っているでしょう。
しかし、実際には副流煙の方が、多くの有害物質を含んでいると言われています。
では、主流煙と副流煙に含まれる有害物質の量には、どのくらいの違いがあるのでしょうか?
主な成分で比較してみると、次のようになります。
● 一酸化炭素 4.7倍
● タール 3.4倍
● ニコチン 2.8倍
こちらは、主流煙に含まれる有害物質の量を1とした場合の副流煙に含まれる有害物質の量を表したものです。
いずれも主流煙よりも多くの有害物質が含まれていることがわかります。
主流煙と副流煙ではどっちが悪いのか、ということですが、副流煙の方が悪いと言えるでしょう。
副流煙(受動喫煙)による健康への影響について
主流煙と副流煙では、含まれている有害物質の量が異なり、主流煙よりも副流煙の方が問題であると解説しました。
副流煙は、非喫煙者にも健康面で大きなリスクがあると言われています。
では、具体的に副流煙による健康への影響とはどのようなものなのでしょうか?
副流煙による健康への影響としては、急性症状と慢性的な影響があると言われています。
急性症状とは、簡単に解説すると、症状が急に現れる、短い期間で症状が出るという意味です。
この急性症状では、眼・鼻・喉などに症状が出ます。
具体的な症状とはしては、次のようなものです。
● 眼の症状
かゆみ・痛み・まばたきの回数が増加・涙が出る
● 鼻の症状
くしゃみ・鼻づまり・鼻水
● 喉の症状
咳・かゆみ・痛み
● その他の症状
頭痛・喘鳴・心拍数増加・末梢血管収縮・循環障害
(参考:急性症状)
上記は、急性影響についてでしたが、次に見ておきたいのが、慢性的な影響についてです。
慢性的な影響として指摘されているのが、次のようなものになります。
● 肺がんリスクの上昇
● 動脈硬化リスクの上昇
● 脳梗塞リスクの上昇
● 心筋梗塞リスクの上昇
また、妊婦・胎児・幼児などへの影響も大きいと言われているのです。
出生体重低下や乳幼児突然死症候群、中耳炎や呼吸器疾患等のリスクが上昇してしまいます。
ですから、副流煙は喫煙をしていない人にも健康面で大きなリスクがあるのです。
パートナーが喫煙をしている、あるいは職場でずっと受動喫煙にさらされているような環境だと、ここで解説したような慢性的な影響が出る可能性が高まります。
タバコの煙と聞くと、喫煙者だけに健康面のリスクがあるように感じるでしょうが、喫煙者だけでなく、非喫煙者にも健康面で大きなリスクがあるのです。
とくに、健康面での影響が大きい、乳幼児や小児の命を奪ってしまう可能性があるということも認識しておかなければなりません。
大切な命を守るためにも、受動喫煙防止を徹底すること、喫煙に関するルールを守ること、周囲に対して十分な配慮を行うことが求められます。
ルールを守らない、配慮を怠るなどした場合には、大きなトラブルに発展してしまうことになりかねません。
十分注意しておきましょう。
喫煙は多くの人が不快に思っている
副流煙による健康への具体的な影響について解説しました。
そのため、受動喫煙を防止することが大切であるということがわかったと思います。
さらに、もう1つ喫煙者が知っておかなければならないことがあるのです。
それは、喫煙は多くの人が不快に思っているということ。
心幸ホールディングス株式会社が行った、タバコの喫煙と業務生産性の関連調査によると、次のような結果が出ているそうです。
● Q1あなたは、同じ部署で働いている喫煙者のタバコ喫煙を不快に思いますか。
・非常にそう思う 29.0%
・ややそう思う 31.8%
・あまりそう思わない 28.0%
・全くそう思わない 9.3%
・わからない/答えられない 1.9%
● Q2 Q1で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。同じ部署で働いている喫煙者のタバコ喫煙を不快に思う理由を教えてください。(複数回答)
・本人からタバコの臭いがするから:80.0%
・タバコ休憩が黙認されているから:43.1%
・タバコ休憩で業務が滞るから:38.5%
・部署の飲み会の際に、喫煙可能なお店になってしまうから:18.5%
・吸い殻のポイ捨てをよく見かけるから:10.8%
・その他:4.6%
・わからない/答えられない:0.0%
(出典:心幸ホールディングス株式会社 「タバコの喫煙と業務生産性の関連調査」)
この調査結果を見てみると、喫煙を不快に思っている人が60.8%もいることがわかります。
また、不快に思う理由として、「本人からタバコの臭いがするから」が代表的な理由として挙げられていました。
ですから、タバコの臭いが不快に感じるという人が多いようです。
受動喫煙を防ぐのはもちろんですが、多くの非喫煙者が不快に感じる、タバコの臭いについても対策が必要と言えるでしょう。
望まない受動喫煙を防止するための対策

多くの非喫煙者が喫煙を不快に思っている、とくにタバコの臭いが不快であると考えていることがわかりました。
では、このような問題を解決するために、どのような対策を行えばよいのでしょうか?
● 屋外に喫煙スペースを設ける
施設の種類によっては、一定の基準をクリアすることで、屋内に喫煙スペースを設置できる場合があります。
喫煙者にとっては、移動時間が少なくて済みますし、利用しやすいというメリットがあるでしょう。
しかし、屋内に喫煙スペースを設置してしまうと、どうしてもタバコの煙や臭いが漏れ出してしまうというリスクがあります。
非喫煙者が不快に思うだけでなく、クレームの増加にもつながる可能性があるのです。
そこで、喫煙スペースを屋内ではなく、屋外にすることで、受動喫煙のリスクを大幅に低減させることができます。
できるだけ、人が普段通らないような場所に喫煙スペースを設置すれば、喫煙者と非喫煙者の共存が可能となるのです。
分煙をすることで、非喫煙者にもメリットがあります。
屋外に設置することで、タバコの煙や臭いがきにならなくなりますし、髪や服などに臭いがついてしまうリスクも大幅に下げることができるのです。
● 禁煙を希望する社員のサポート
分煙以外の対策として挙げられるのが、喫煙をしている社員の中で、禁煙を希望する社員のサポートを行うというもの。
喫煙をする社員が多ければ多いほど、当然ですが、受動喫煙のリスクが高まってしまいます。
ですが、そもそも喫煙をする社員が少なければ、リスクも低減することができるでしょう。
ですから、禁煙を希望する社員に対しては、企業側がサポートをしてあげるのがよいと考えられます。
サポート言ってもさまざまなサポートの仕方がありますが、一般的に行われているものとしては、禁煙外来にかかる費用の補助です。
禁煙外来にかかる費用を一部もしくは全額負担することで、喫煙者が禁煙しやすい環境を構築するというもの。
費用がかかると聞くと、通うのを諦めてしまう人もいるでしょうが、費用の一部であってもサポートをしてあげれば、チャレンジしやすくなるでしょう。
受動喫煙防止対策を行うための重要なポイント
具体的な対策として、2つの対策を紹介しました。
ただし、ここで注意しておかなければならないことがあります。
その注意点としては、急がないこと・一方的に悪と決めつけてしまわないことです。
受動喫煙防止対策のために、すでに設置されていた喫煙スペースをすべて撤去するなどを行うと、喫煙者の大きな反発を招く恐れがあります。
反発を招くと、関係が悪化するだけでなく、社内の人間関係にも悪い影響を及ぼす可能性があるのです。
そこで重要となるのが、一方的に喫煙者に押しつけるのではなく、丁寧に説明をして、こちらに協力してもらうということ。
例えば、喫煙スペースを撤去するにしても、いきなりすべての喫煙スペースを撤去する、あるいは数を減らすなどすると、強い反発を受ける可能性があります。
ですから、周知徹底を行い、段階的に対策を進めるのがよいでしょう。
喫煙スペースについては、タバコミュニケーションという言葉があるように、喫煙が社内でのコミュニケーションになっている場合もあると思いますが、さまざまな代替策があるため、そちらを検討してみるのがおすすめです。
● 教育などを行う
それから、その他で大切となるのが教育。
教育というのは、タバコによる健康リスクや喫煙者だけでなく、非喫煙者にも影響を及ぼすことなどです。
喫煙者の中には、どのような健康リスクがあるのか、他人の健康面にも悪影響を及ぼすということを理解していない人がいます。
ですから、外部から講師を招き、喫煙に関するリスクや望まない受動喫煙のリスクなどの教育を行っておくのがよいでしょう。
● 社用車にも対策を行う
望まない受動喫煙を防止するということが、ルール化されています。
そこで、必ず押さえておきたいポイントがあるのです。
そのポイントとは、建物内だけでなく、社用車にもしっかりとしたルールを設けるということ。
企業によっても異なりますが、建物内にはしっかりとルールを設けているのに、社用車には明確なルールを決めていないというケースが多くなっています。
ルールが曖昧になってしまうと、喫煙者が勝手に喫煙をしてしまう可能性がありますし、非喫煙者の同乗者が乗ったときに、不快に思ってしまう場合があるでしょう。
また、複数の社員が社用車を使っている場合も、注意しなければなりません。
喫煙者である社員が車内で勝手に喫煙をすると、車内に臭いや有害物質が残ってしまうことになるので、望まない受動喫煙が生じるリスクが高まります。
ですから、社用車の車内では禁煙にするようにルールを決めておくとよいでしょう。
空気清浄機を設置するだけでは受動喫煙防止はできない
喫煙については、多くの非喫煙者が不快に思っていると解説しました。
このような問題を解決する場合、多くの人が検討するのが、空気清浄機を設置するというものです。
空気清浄機を設置することで、「受動喫煙防止ができるのではないか?」と考える人もいるでしょう。
結論から言えば、空気清浄機を設置しただけでは、望まない受動喫煙を防止することはできません。
その理由としては、空気清浄機を設置しただけでは、タバコに含まれている有害物質を除去することができないからです。
空気清浄機を設置することで、タバコの嫌な臭いを軽減させることはできるでしょう。
しかし、すでに解説しているように、タバコには多くの有害物質が含まれています。
これらを除去することができないため、設置しても受動喫煙防止対策にはならないのです。
受動喫煙対策は専門家に相談するのがおすすめ
副流煙には、多くの有害物質が含まれており、しっかりとした対策が必要となります。
ですが、「何からすればよいのだろうか?」「どのような対策を行えばよいのか?」など悩んでしまうケースも珍しくないでしょう。
そのような場合には、専門の業者に相談するのがおすすめです。
専門業者であれば、法律に基づいた、それぞれに合った提案を行ってくれます。
弊社では、分煙コンサルタントを配置しておりますので、分煙に関することならお気軽にご相談ください。
▼導入実績はコチラから
施設別導入事例
まとめ
タバコの煙には、主流煙や副流煙があります。
どちらもタバコの煙ですが、副流煙の方が、主流煙よりも多くの有害物質が含まれていると言われているのです。
また、副流煙による健康へのリスクも懸念されています。
望まない受動喫煙を防止するためには、屋外に喫煙スペースを設けることや禁煙を希望する社員の禁煙に向けたサポートを行うことが大切です。
何から始めたらよいのかわからないという場合には、お気軽にご相談ください。