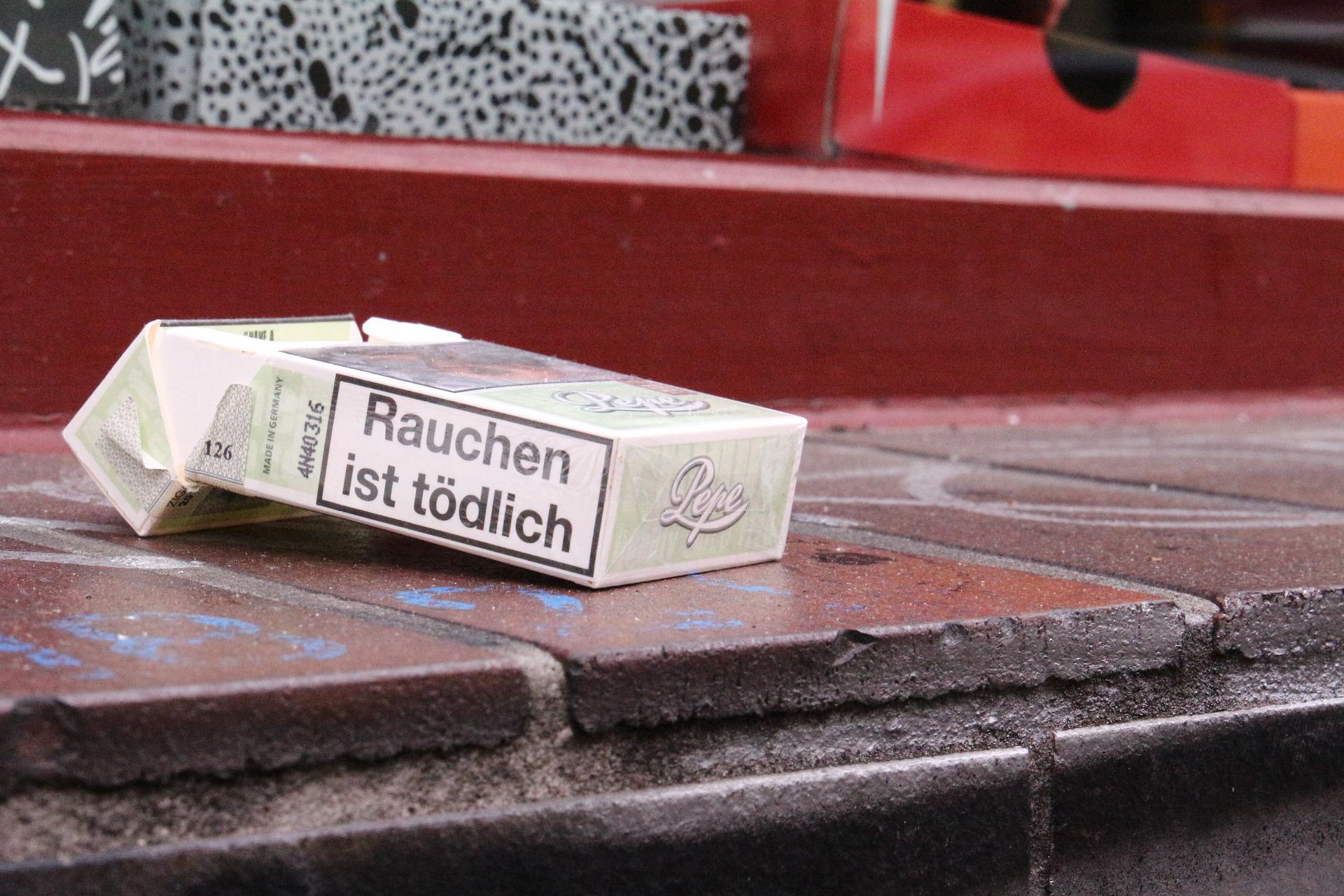2025.10.07
喫煙所コラム
タバコミュニケーションは無理?非喫煙者向けの代替策とは?

皆さんは、「タバコミュニケーション」という言葉を聞いたことがありますか?
喫煙者の方であれば、知っていると思いますが、非喫煙者の中には、否定的な人もいるようです。
では、非喫煙者向けの代替策には、どのようなものがあるのでしょうか?
今回のコラムでは、非喫煙者も参加できる代替策について解説します。
タバコミュニケーションで仕事が円滑になることがある
皆さんの職場で、「タバコミュニケーション」という言葉を聞いたことがありますか?
日本では、喫煙に関する法律が改正され、喫煙者にとっては非常に厳しい環境となっているため、以前のようにタバコミュニケーションが活発に行われることは少なくなっているかもしれません。
まず、「タバコミュニケーションとは何か?」についてですが、これは簡単に解説すると、喫煙者同士が喫煙所で行うコミュニケーションのことです。
喫煙をしながら、仕事の話やプライベートの話をすることで、コミュニケーションを図ることで、関係が良好になる、仕事が円滑に進む、などのメリットがあるとされています。
クリニックフォアグループが喫煙者を対象に行った調査によると、次のような結果が出ているそうです。
Q職場でのコミュニケーションが、喫煙本数や喫煙に費やす時間に影響していると感じますか?
・とても感じる 27%
・感じる 61%
・どちらかというと感じる6%
・どちらかというと感じない 3%
・感じない 3%
・まったく感じない 0%
Q働くうえで感じる喫煙のメリットを教えてください
・喫煙者や喫煙者同士だと業務にまつわる相談や会話がしやすい 37%
・オンオフの切り替えがしやすい 32%
・仕事によるストレスが和らぐ 29%
・所属や役職などを超えて喫煙者同士仲良くなりやすい 23%
・転職や昇進が有利になる 16%
・とくにプラスに感じたことはない 18%
・その他 1%
Q喫煙所でのコミュニケーションやたばこ休憩を通じて、仕事が円滑に進んだと感じたことはありますか?
・とてもある 15%
・ある 37%
・どちらかといえばある 22%
・どちらかというとない 10%
・ない 11%
・まったくない 5%
(出典:クリニックフォアグループ「タバコミュニケーションに関する調査」)
この調査結果を見てみると、職場でのコミュニケーションが喫煙本数や時間に影響していると感じている人が95%もいることがわかります。
また、働くうえで感じる喫煙のメリットについては、「喫煙所や喫煙者同士だと業務にまつわる相談や会話がしやすい」「オンオフの切り替えがしやすい」「仕事によるストレスが和らぐ」などが上位です。
さらに、タバコミュニケーションによって、仕事が円滑に進んだことがあると感じたことがある人は、74%となっています。
ですから、この調査結果を見てみると、タバコミュニケーションには一定の効果を期待することができそうです。
さまざまなデメリットもある
最初に、タバコミュニケーションとは何か、どのようなメリットがあるのか、について解説しました。
メリットを考えると、仕事が円滑に進む可能性があるため、とても良いものと認識してしまう人も多いでしょう。
しかし、実際にはメリットだけでなく、さまざまなデメリットも存在します。
そのデメリットとは、具体的に次のようなものです。
● 非喫煙者が参加しづらい
仕事が円滑に進むようになるというのはよいことですが、あくまでも喫煙を通じてコミュニケーションを図ることになるため、非喫煙者が参加しづらいというデメリットがあります。
もちろん、20歳以上であれば、喫煙をしなくても職場の喫煙所に立ち入ることはできますが、タバコの煙や臭い、また受動喫煙のリスクがあることなどから、参加するのが難しくなってしまいます。
● 喫煙者と非喫煙者で情報格差が生まれる可能性がある
それから、タバコミュニケーションのデメリットとして挙げられるのが、喫煙者と非喫煙者で情報格差が生まれる可能性があるということです。
喫煙者であれば、喫煙を通じてさまざまな情報交換を行うので、社内・社外の情報が入りやすくなります。
しかし、非喫煙者の場合は、喫煙をしないので、そこで行われる情報交換に加われないため、情報が入手できず、格差が生まれてしまう場合があるのです。
● 健康リスクが増大する可能性がある
また、最も注意しなければいけないのが、健康リスクが増大する可能性があるということ。
喫煙をするだけでも、大きな健康リスクがありますが、タバコミュニケーションによって、そのリスクが増大してしまう可能性があるのです。
例えば、コミュニケーションのために、頻繁に喫煙所へ向かう、同僚や他部署、上司や部下などと話が弾み、毎回喫煙する本数が増えてしまうなどのケース。
喫煙の本数が増えてしまえば、当然ですが、健康リスクも増大してしまう可能性が高まります。
仕事が円滑に進むようになったとしても、健康リスクが増大してしまえば、意味がなくなってしまいます。
健康リスクで言えば、肺がん・脳卒中・心筋梗塞などのリスクが高まるでしょう。
● 評価が下がってしまうリスク
タバコミュニケーションによって、期待できる効果についてはすでに解説していますが、だからといって、頻繁に行っていれば、周囲からの評価が下がってしまう可能性があるでしょう。
「1日に何度も休憩をしている!」「また仕事をサボっている!」「喫煙者だけ何度も休憩をするのはズルい!」など評価が下がってしまうケースや信頼を失ってしまうケース、不公平感が生まれてしまうケースなどが考えられます。
ですから、喫煙者同士では良好な関係を築くことができても、喫煙者と非喫煙者では良好な関係を築くことができない場合もあるのです。
非喫煙者も参加できる代替策が必要
タバコミュニケーションには、ここまで解説してきたように、メリットもありますが、デメリットも多く存在しています。
そのため、喫煙者だけが参加できるコミュニケーション方法を選択するのではなく、非喫煙者も参加可能な、タバコミュニケーションの代替策が必要です。
喫煙を通じてコミュニケーションを図るのではなく、喫煙以外の方法でコミュニケーションを図ることが重要となります。
それから、しっかりと理解しておかなければならないのが、非喫煙者の多くは、タバコミュニケーションを受け入れていないということです。
喫煙者同士であれば、有効なコミュニケーション手段となるかもしれませんが、非喫煙者にとっては、有効なコミュニケーション手段とは認識していません。
その点についても理解しておきましょう。
具体的な代替策について
タバコミュニケーションには、メリットもあるが、デメリットも多く、また非喫煙者は健康リスクへの懸念から、有効なコミュニケーション手段とは認識していないと解説しました。
そのため、タバコミュニケーションの代替策が必要です。
では、代替策としてどのようなものがあるのでしょうか?
● コミュニケーションスペースの設置
主な代替策として挙げられるのが、コミュニケーションスペースの設置です。
これまで、喫煙所で行われていたコミュニケーションを新たに設置したコミュニケーションスペースで行うというもの。
コミュニケーションスペースの設置には、さまざまなメリットがあります。
社員が気軽に立ち寄ることができるので、同じ部署だけでなく、他部署の社員とも気軽にコミュニケーションをとることができるのです。
また、部署だけでなく、役職も関係なくコミュニケーションをとりやすいというのも大きなメリットとなります。
タバコミュニケーションとの大きな違いは、「喫煙を通さずにコミュニケーションがとれること」。
だから、喫煙者も非喫煙者も関係ないというのが大きなポイントです。
さらに、気軽に利用できることから、仕事やプライベートでの悩みを相談しやすくなるのも魅力と言えるでしょう。
緊張した状態では、なかなか相談できないことも、リラックスした状態であれば、相談しやすくなります。
● コミュニケーションランチ制度の導入
コミュニケーションスペースの設置の他では、コミュニケーションランチ制度の導入もあります。
この制度は、社内交流を目的とした制度の1つで、部署や役職などを超えて、社内のさまざまな人が一緒にランチをするという制度です。
これまで、あまり関りがなかった人とも、ランチを通じてつながるきっかけができるので、大きな魅力があると言えます。
また、企業によっては、同じく社内交流を目的として、飲み会を行うところがありますが、コミュニケーションランチの方が飲み会よりも参加しやすくなっているのです。
飲み会の場合には、通常勤務後に行われることになります。
そのため、酒を飲まない人や飲み会が好きではないという人からすると、プライベートな時間を犠牲にしている、参加したくない、と考える人も多いのです。
さらに、子育て中の方などは、子どもの世話があるため、飲み会に参加できないケースもあります。
ですが、コミュニケーションランチであれば、昼に行われるので、子育て中の人でも参加しやすいですし、プライベートな時間を犠牲にすることもありません。
その点から、飲み会よりも参加しやすいと言えるでしょう。
一般的に、ランチ代は企業が負担するため、参加者は金銭的な負担がなく、さまざまな人と交流することができます。
企業によっては、外国人が働いている場合もあると思いますので、外国人とのコミュニケーションを図るという意味でもコミュニケーションランチは有効と言えるでしょう。
● 部活・サークル活動
その他では、部活・サークル活動が代替策として挙げられるでしょう。
部活やサークル活動と聞くと、学生時代の頃を思い出す人が多いと思いますが、企業でも部活やサークル活動を行っているところがあります。
こちらも社内のコミュニケーションを活性化させるのに有効です。
部活やサークル活動と聞くと、スポーツ系のものをイメージする人が多いと思いますが、スポーツ系だけでなく、文科系のものなどもあるようです。
それから、企業によって異なるようですが、兼部も認められており、複数の部に所属している社員もいます。
もちろん、1つの部に所属するだけでも、社内コミュニケーションの活性化につながりますが、複数の部に所属することで、さらに多くの人と交流することができるのです。
タバコミュニケーションよりもずっと健康的に、多くの社員とつながれるのが大きな魅力と言えるでしょう。
若手とベテラン社員が一緒に活動することで、信頼関係を構築できる場合もあります。
部活やサークル活動は、自分が興味のあるもの、好きなものを選ぶことができるので、社員も選びやすいですし、同じ趣味の人とつながれるのも良い点と言えるでしょう。
代替策を検討する際は社内アンケートを実施するのがおすすめ
タバコミュニケーションの代替策としていくつかの代替策をとりあげました。
使える予算やスペースなどの問題があるため、すべてを実行するのは不可能と言えるでしょう。
また、それぞれの企業によって、有効なものが異なると考えられます。
そのため、社員の意見を幅広く聞くために、社内アンケートを実施するのがおすすめです。
社内アンケートのメリットは、社員の本音や考えていることが聞けるということ。
それから、企業が社員の声に耳を傾けることで、社員の満足度の向上にもつながります。
一般的な企業では、喫煙者と非喫煙者が混在していますので、喫煙者だけあるいは非喫煙者だけの意見を採用するのではなく、両者の意見を聞いて、両者が共存できるような環境を整えることが重要です。
喫煙者は、タバコミュニケーションで満足しているかもしれませんが、非喫煙者はそれでは満足していません。
その点についてしっかりと理解しておきましょう。
タバコミュニケーションには、たしかにメリットがありますが、デメリットも多く、健康リスクが増大する可能性があります。
ですから、現在タバコミュニケーションだけ行っているという場合には、早めに代替策について検討する必要があるでしょう。
まとめ
タバコミュニケーションは、喫煙を通じてコミュニケーションを図ることです。
メリットもありますが、デメリットも多く、非喫煙者が参加しづらいため、代替策について検討する必要があります。
代替策は、コミュニケーションスペースの設置やコミュニケーションランチ制度の導入、部活・サークル活動などです。
社内の意見を聞いて、それぞれにあったものを選びましょう。