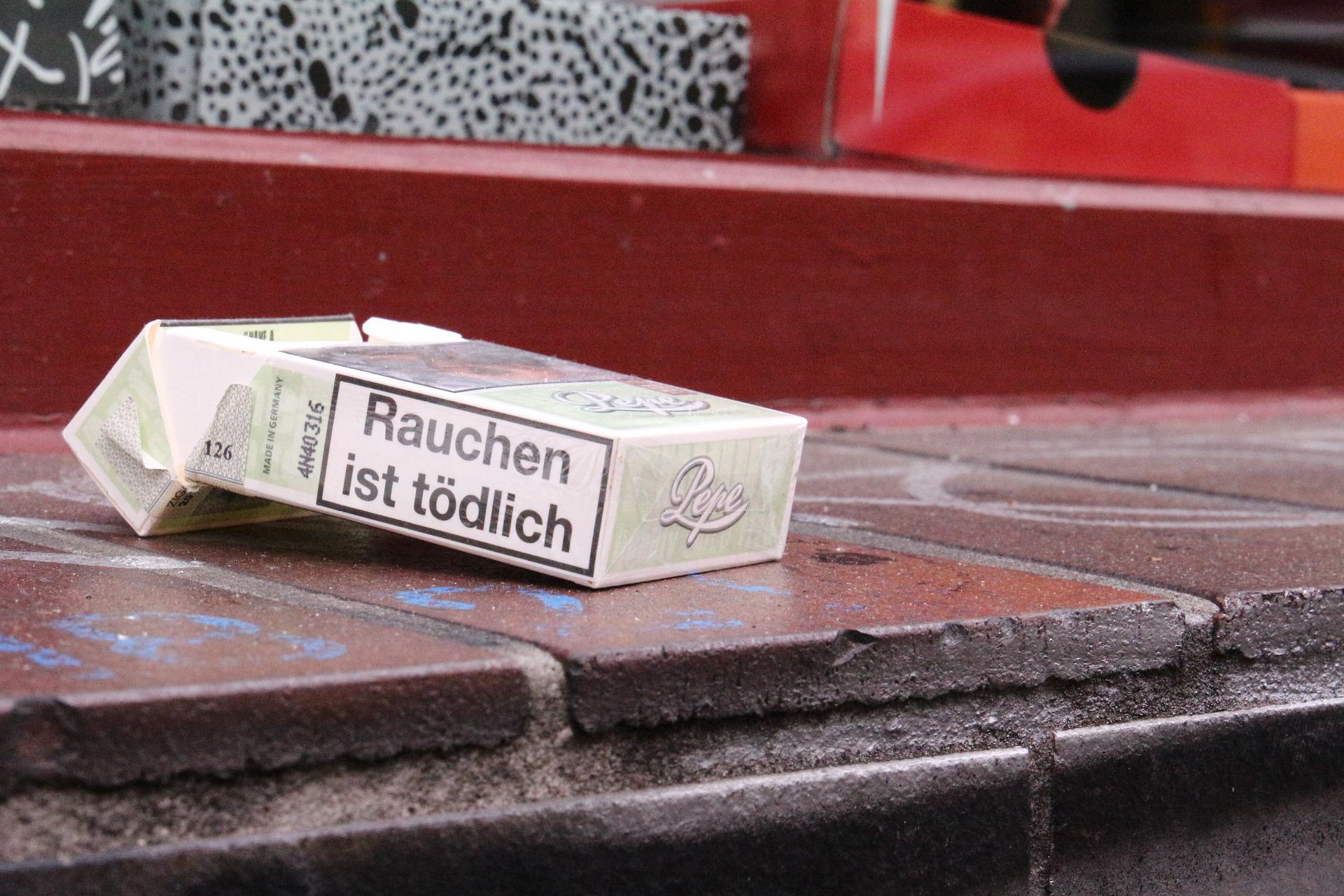2025.03.03
喫煙所コラム
喫煙者と非喫煙者の多様性を実現するためにできることとは?

現代では、「多様性」という言葉を耳にすることがありますが、正確にその意味を理解している人は少ないでしょう。
今回のコラムでは、多様性の意味や喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築するために、できることについて解説します。
多様性とは異なる特徴や特性を持つ人がともに存在すること
皆さんは、多様性という言葉を聞いたことがありますか?
現代では、さまざまなところで、多様性という言葉を聞くことがあります。
この多様性とは、辞書的な意味では、「異なる特徴や特性を持つ人がともに存在すること」です。
もう少しわかりやすく解説すると、年齢・性別・国籍・価値観・信条・宗教などが異なる人を尊重するということになります。
また、尊重するだけでなく、それぞれの違いを認めるという意味でも使われることがあるのです。
これまでは、多様性に対する取り組みを行っていなかった企業が多くなっていましたが、今後は多様性に対する取り組みを行う企業も増えていく可能性があります。
多様性の観点から喫煙者と非喫煙者の共存を考える
最初に、多様性について簡単に解説しました。
年齢・性別・国籍・価値観などが異なる人を尊重する、違いを認めるというものでしたが、一般企業の中では、多様性の観点からもう1つ考えなければいけないことがあります。
それは、喫煙者と非喫煙者が混在しているということです。
どちから一方にとって快適な環境を整えるということではなく、混在している状況の中では、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を整えることが非常に重要であると言えます。
法律の改正によって、受動喫煙防止がルール化されていますが、喫煙者と非喫煙者が共存できていないというケースも少なくないようです。
ですから、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築する必要があります。
タバコの臭いやタバコ休憩に関する問題を解決しなければならない
多様性の観点から、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築することが大切と解説しました。
そこで、押さえておかなければならないのが、非喫煙者が喫煙者に対して、どのように感じているのか、ということです。
この点を理解しておかないと、喫煙者が非喫煙者に受け入れてもらうことができず、共存できる環境を構築するのが難しくなってしまいます。
心幸ホールディングス株式会社が、喫煙者と同じ部署で働いている非喫煙者の会社員107名を対象に行った調査によると、次のような結果が出たそうです。
● Q1.あなたは、同じ部署で働いている喫煙者のタバコ喫煙を不快に思いますか。
・ 非常にそう思う 29.0%
・ ややそう思う 31.8%
・ あまりそう思わない 28.0%
・ 全くそう思わない 9.3%
・ わからない/答えられない 1.9%
● Q2.同じ部署で働いている喫煙者のタバコ喫煙を不快に思う理由を教えてください。(複数回答)
・ 本人からタバコの臭いがするから:80.0%
・ タバコ休憩が黙認されているから:43.1%
・ タバコ休憩で業務が滞るから:38.5%
・ 部署の飲み会の際に、喫煙可能なお店になってしまうから:18.5%
・ 吸い殻のポイ捨てをよく見かけるから:10.8%
・ その他:4.6%
・ わからない/答えられない:0.0%
● Q4.同じ部署に喫煙者がいることで起こる職場への影響を教えてください。(複数回答)
・ タバコの臭いにより周りの印象が悪くなること:49.5%
・ 休憩時間が不均衡になること:43.9%
・ 空気の質が落ちること:33.6%
・ 喫煙者が近くにいると非喫煙者の健康被害が出ること:28.0%
・ 業務が滞ること:21.5%
・ 周りの人の集中力が切れ、業務生産性が落ちること:15.9%
・ その他:0.0%
・ 特にない:15.9%
・ わからない/答えられない:0.9%
(出典:心幸ホールディングス株式会社 タバコの喫煙と業務生産性の関連調査)
この結果を見てみると、全体の6割以上の人が、喫煙者のタバコ喫煙を不快に思っていることがわかります。
それから、不快に思う理由としては、「本人からタバコの臭いがするから」「タバコ休憩が黙認されているから」「タバコ休憩で業務が滞るから」などが上位に挙げられています。
さらに、職場への影響という点では、「タバコの臭いにより周りの印象が悪くなること」「休憩時間が不均衡になること」「空気の質が落ちること」などが上位。
ですから、喫煙者と非喫煙者の共存を可能にするためには、このような課題を解決しなければなりません。
脱臭機の導入やタバコ休憩に関するルールを決めることが大切
さきほど解説したように、非喫煙者の多くは、タバコの臭いやタバコ休憩の問題が気になっていると考えられます。
この問題を解決することができなければ、共存することが難しくなるでしょう。
● 脱臭機の導入
非喫煙者の多くが気になっているのが、タバコの臭いについてです。
すべての臭いを取り除くのは難しいですが、喫煙所からタバコの煙が漏れないようにすることと、脱臭機を導入するのがよいでしょう。
脱臭機であれば、タバコの臭いを除去してくれます。(※製品によっても異なりますが、すべての臭いが完全に取り除けるわけではありません)
● 消臭スプレーを活用する
喫煙所から漏れ出すタバコの臭いだけでなく、喫煙者の衣服についたタバコの臭いが気になるという人も多くなっています。
このような場合には、消臭スプレーを活用するとよいでしょう。
最近では、タバコの臭い向けの消臭スプレーが販売されています。
もちろんこちらも、完全にタバコの臭いを取り除けるというわけではありませんが、喫煙後に使用することで、臭いを抑えることができるでしょう。
● タバコ休憩に関するルールを決める
タバコの臭い以外で、非喫煙者が気になっているのが、タバコ休憩に関する問題です。
タバコ休憩に関するルールが曖昧になっていると、喫煙者だけが非喫煙者よりも多く休憩をとれることになってしまうので、不平等であると感じる人が多くなっています。
非喫煙者に不平等と思われないようにするためには、タバコ休憩に関するルールをしっかりと決めることが大切です。
また、ルールを決めるだけでなく、ルールを守らなかった場合にはどうするか、についてもしっかりと議論をしておくとよいでしょう。
タバコ休憩に関するルールが明確になっており、ルールを守らなかった場合の対応も決められていれば、非喫煙者の社員が不平等と感じることも少なくなるはずです。
お互いを尊重しなければ退職など人材流出につながる恐れがある
喫煙者と非喫煙者が混在している状況では、両者の意見をしっかりと聞き、お互いを尊重することが重要となります。
どちらかの意見しか聞かないとなれば、退職を検討する社員も出てくるでしょう。
もしも、優秀な社員が退職を検討して、そのまま退職してしまえば、貴重な人材が流出してしまうことになります。
優秀な人材を失うことは、企業にとって大きな損失となるでしょう。
優秀な人材を失わないためにも、喫煙者と非喫煙者の意見を聞き、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築することが重要となります。
弊社では、分煙コンサルタントを配置しておりますので、分煙に関することなどお気軽にご相談ください。
▼導入実績はコチラから
施設別導入事例
まとめ
一般企業では、喫煙者と非喫煙者が混在しています。
多様性の観点から、どちらか一方を優遇するのではなく、喫煙者と非喫煙者の共存が可能な環境を構築することが重要です。
とくに、タバコの臭いやタバコ休憩に関する問題が指摘されていますので、これらの問題を解決することも必要となります。