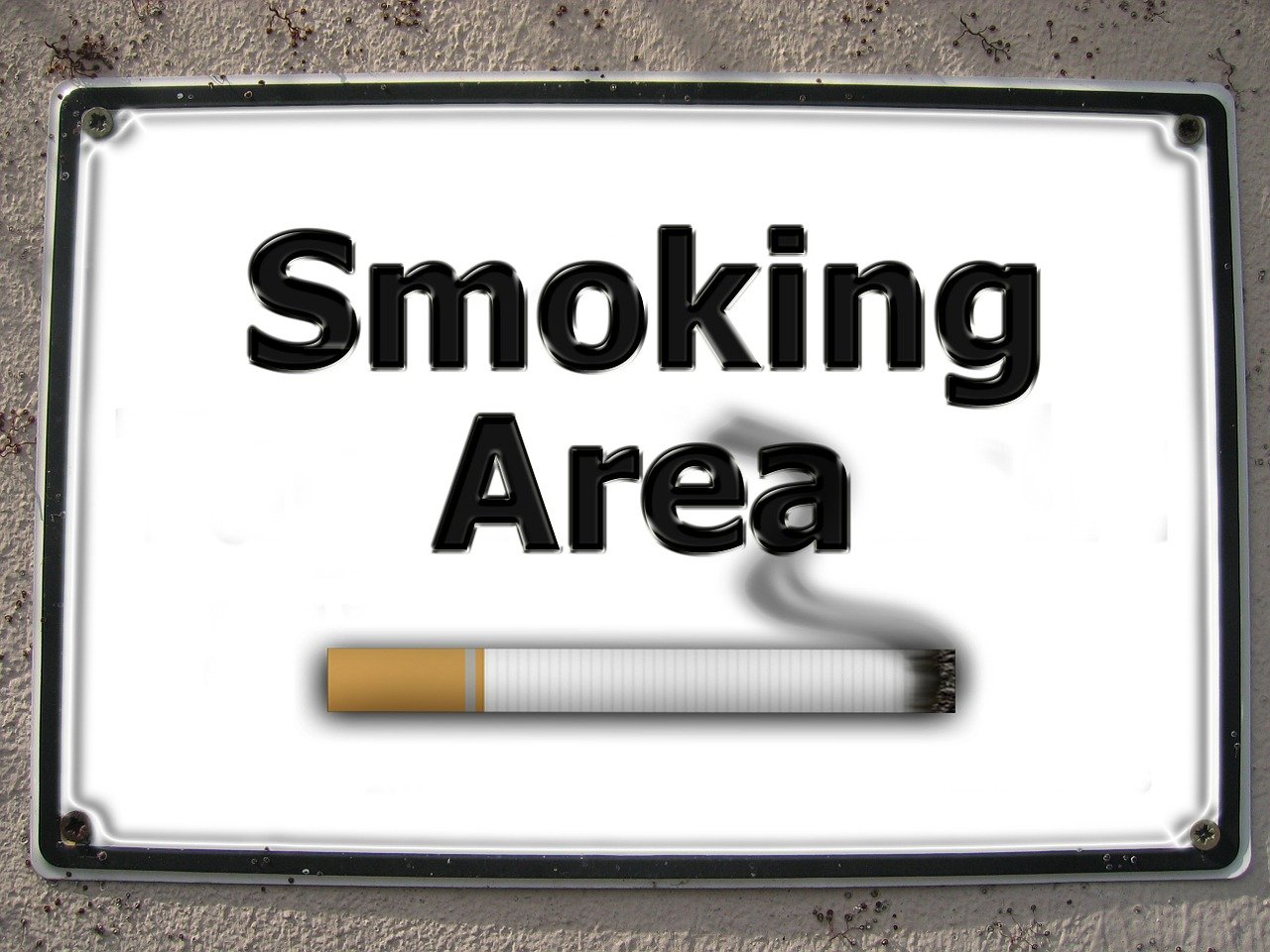2021.04.19
分煙対策・受動喫煙対策
受動喫煙防止法をわかりやすく解説!何が変わるのか?

日本では、喫煙に関する法律改正が行われました。
しかし、その目的や変更点などについては、あまり正しく理解していないという人が多いようです。
今回のコラムでは、法律改正の目的や変更点について詳しく解説します。
また、法律改正によって、企業が行うべきことについても理解しておきましょう。
法律改正の目的とは?
日本では、健康増進法の一部を改正する法律が施行されています。
では、どうして法律改正となったのでしょうか?
その目的については、主に次の3つがあります。
・「望まない受動喫煙」をなくすこと
・受動喫煙による健康への影響が大きいと考えられる子どもや患者等に配慮すること
・施設や場所ごとに対策を行うこと
(参考:健康増進法の一部を改正する法律概要)
法律改正前には、喫煙に関するさまざまな問題がありました。
とくに、大きな問題となっていたのが、望まない受動喫煙に関する問題です。
受動喫煙は、喫煙者だけでなく、非喫煙者の健康にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、大きな問題となっていました。
法律改正によって、望まない受動喫煙を防止すること、子どもや患者に配慮すること、それぞれに必要な対策を行うことがルール化されるようになりました。
受動喫煙の影響とは?
喫煙による健康への影響は、喫煙者だけの問題と考えてしまいがちですが、喫煙者以外にも健康への影響が懸念されています。
喫煙者が吸い込むたばこの煙だけでなく、たばこから出る煙、そして喫煙者が吐き出す煙についても多くの有害物質が含まれていることが指摘されているのです。
そのため、望まない受動喫煙によって、非喫煙者にも健康被害が出る恐れがあります。
具体的にどのような健康被害が出るのか、についてですが、代表的なものは次のようなものです。
・肺がん
・脳卒中
・虚血性心疾患
・乳幼児突然死症候群(SIDS)
また、日本では年間約15,000人が受動喫煙によって死亡していると推計されているのです。(参考:厚生労働省 e-ヘルスネット)
このように、受動喫煙によって多くの人に健康被害が出る恐れがあります。
また、子どもや妊婦にもその影響は大きく、妊婦の場合には、早産や低体重児のリスクが高まるとも言われているのです。
そのため、望まない受動喫煙を防止することが重要となります。
何が変わったのか?
最初に解説したように、健康増進法の一部が改正されましたが、具体的に「何が変わったのか?」よくわからないという人も多いでしょう。
法律改正の大きなポイントは、望まない受動喫煙を防止するための対策がマナーからルール化されたことです。
これまでの法律では、あくまでもマナー(努力義務)となっていましたが、法律改正によってルール化(義務化)されています。
ルール化によって変更された4つのポイントは次の通りです。
① 多くの施設では屋内が原則禁煙となった
② 屋内で喫煙を行う場合には喫煙室を設置する必要がある(施設の種類によって設置できない場合もある)
③ 20歳未満は従業員であっても喫煙エリアに立ち入ることはできない
④ 喫煙室については標識掲示が義務付けられている
それから、必ず押さえておかなければいけないのが、違反した場合には罰則があるということです。
行政による指導や処分はもちろんですが、過料の罰則が適用される場合もあります。
過料の罰則では、違反した内容によって異なりますが、50万円以下の過料となる場合もあるため、違反しないように正しく理解をすることが大切です。
施設ごとのルールについて
法律改正のポイントについて簡単に解説しましたが、それ以外で押さえておかなければならないのが、「施設の類型・場所によってルールが異なる」ということです。
学校・病院・行政機関の庁舎・児童福祉施設等の第一種施設では、「敷地内禁煙」というルールとなっています。
敷地内禁煙では、敷地内のマイカー内での喫煙もルール違反となっており、屋外において受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)に喫煙場所を設置ができるというルールです。
施設の種類の中では、最も厳しいルールとなっています。
事務所・宿泊施設・飲食店・工場などの第二種施設では、「原則屋内禁煙」というルールです。
屋内において喫煙をする場合には、一定の基準をクリアした喫煙専用室等の設置が必要となります。
また、第二種施設の屋外については、規制の対象外です。
ここまで解説してきたように、第一種施設と第二種施設では、ルールが異なります。
第一種施設の方が厳しいルールとなっており、第二種施設の屋外は規制の対象外となっている点も大きな違いと言えるでしょう。
屋内に設置可能な喫煙室の種類について(※第一種施設を除く)
第一種施設では、敷地内禁煙となっているため、屋内に喫煙室を設置することはできません。
しかし、第二種施設においては、一定の基準をクリアしなければなりませんが、屋内に設置可能な喫煙室があります。
設置が可能な喫煙室について見ていきましょう。
設置が可能なのは、4タイプです。
喫煙専用室
喫煙は可能ですが、飲食等は不可となっており、施設の一部に設置することができます。
一般的な事業者が設置できるタイプの喫煙室です。
加熱式たばこ専用喫煙室
喫煙は可能ですが、加熱式たばこに限定されているのが大きなポイントとなります。
また、飲食等が可能で、施設の一部に設置が可能です。
一般的な事業者が設置できますが、こちらは経過措置となっています。
喫煙目的室
こちらは、喫煙が可能で飲食等も可能(主食を除く)で、施設の全部もしくは一部に設置ができます。
ただし、喫煙目的室を設置することができるのは、喫煙目的施設に限定されており、一般的な事業者が設置することはできません。
喫煙可能室
こちらも喫煙が可能で飲食等が可能となっており、施設の全部もしくは一部に設置が可能です。
経過措置となっており、既存特定飲食提供施設が設置できるタイプとなっています。
第二種施設では、喫煙専用室もしくは加熱式たばこ専用喫煙室の設置ができることを覚えておきましょう。
注意事項
さきほどは、設置できる喫煙室の種類について解説しましたが、無条件で設置ができるという意味ではありません。
3つの技術的基準をクリアしなければならないのです。
この3つの技術的基準とは、次のようなものになります。
① 出入口における室外から室内への風速が毎秒0.2m以上となっていること
② 壁や天井等で区画されていること
③ たばこの煙が屋外に排気されていること
ですから、屋内に喫煙室を設置する場合には、技術的基準を確認して、クリアできるものを設置しなければならないのです。
屋内に喫煙室を設置する場合には、技術的基準をクリアしなければならないと解説しました。
そのような話を聞くと、規制の対象外となっている屋外に喫煙可能な場所を設置すればよいのではないか、と考える人もいるでしょう。
たしかに、第二種施設の屋外については、屋内よりも比較的簡単に喫煙可能な場所を設置することができます。
ですが、クリアしなければ技術的基準はないものの、「配慮義務」がある点に注意しなければなりません。
この配慮義務については、具体的に決められているわけではありません。
しかし、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をすることや子ども・患者・妊婦等の配慮が必要な人の近くなどでは喫煙をしない等の配慮が必要です。
また、この配慮義務というのは喫煙者だけの話ではありません。
灰皿や喫煙場所を設置する管理者等についても同様に配慮しなければならないのです。
例えば、人通りの多い場所に灰皿を設置しない、営業時間外については灰皿を片付ける等の配慮が必要となります。
規制されていないからという理由で、配慮を怠った場合には、周囲の人と大きなトラブルになってしまう恐れがあるでしょう。
大きなトラブルになってしまった場合には、関係が悪化するだけでなく、最悪の場合には訴訟に発展してしまうことも考えられます。
そのため、無用なトラブルを防ぐためにも配慮義務を怠らないように注意が必要です。
配慮義務については、自宅でも同様に必要となります。
とくに、賃貸物件の場合にはベランダで喫煙すると、近隣にたばこの煙が流れ込んでしまうので注意しましょう。
企業がするべき取り組みとは?

第二種施設においては、次の方法の中から、選択することができます。
「屋内全面禁煙」「分煙(喫煙専用室等の設置)」です。
屋内全面禁煙とは、その名称からもわかるように、屋内を全面禁煙とするもの。
全面禁煙とすることで、望まない受動喫煙を防止することができるというメリットがあります。
しかし、その一方で喫煙者は喫煙をすることができないので、不満が募る可能性があるでしょう。
また、近くの喫煙可能場所に多くの従業員が集まってしまい、周囲からクレームを受けるという恐れもあります。
屋内全面禁煙の他には、分煙を選択することも可能です。
分煙とは、簡単に解説すると喫煙ができる場所を決めて、それ以外の場所を禁煙にするという方法のこと。
喫煙可能な場所として、喫煙専用室等を設置しておくことで、喫煙者と非喫煙者の共存を可能にすることができます。
全面禁煙としてしまうと、どうしても喫煙者の不満が大きくなってしまいますが、分煙であれば喫煙者の不満も抑えることができるでしょう。
企業は、法律に基づいて望まない受動喫煙を防止するのはもちろんですが、喫煙に関するルールの周知徹底を行い、適切に管理を行うことが大切です。
それから、企業の取り組みについては従業員や責任者だけが行うというものではなく、企業全体で行わなければなりません。
一部の従業員だけが努力していて、経営陣がルールを守らないなどの状況では、十分な受動喫煙防止対策を行うことはできないでしょう。
経営陣はもちろん、管理者や従業員等が一体となって、望まない受動喫煙を防止、十分な受動喫煙防止対策を行うことが求められます。
▼導入事例はコチラから
施設別導入事例
受動喫煙と健康経営
最近では、健康経営という言葉を耳にするようになりました。
この健康経営とは、従業員などの健康管理について経営的な視点でとらえて、戦略的に実践することと言われています。
従業員の健康のために、力を入れることで、生産性の向上や組織全体の活性化などが期待されているのです。
この健康経営のためにも、受動喫煙防止は非常に重要となります。
十分な受動喫煙防止対策を行っていなかった場合には、従業員が受動喫煙によって、健康面で大きなリスクを負うことになってしまうからです。
また、企業によっては、受動喫煙防止対策はもちろんですが、従業員の禁煙をサポートするためにさまざまな取り組みを行っています。
例えば、禁煙治療にかかる費用の補助を行う、禁煙プログラムの実施や禁煙に関するセミナーの開催などです。
ここで挙げたのはあくまでも、一部の取り組みですが、禁煙に向けてサポートを行うことで、従業員の健康面でのサポートを行っています。
その他では、全面禁煙を行っているところもあるようです。
ただし、一般的な事業所では喫煙者と非喫煙者が混在していますので、喫煙者から不満が出てしまう恐れがあります。
全面禁煙を行うことも1つの方法ですが、それ以外にも分煙を行うなどでも受動喫煙防止対策を行うことが可能です。
ですから、いきなり全面禁煙とするのではなく、従業員に対して受動喫煙防止対策や望まない受動喫煙を防止する大切などを理解させて、喫煙者と非喫煙者が共存できる環境を構築することが重要となります。
弊社では、専門の分煙コンサルタントを配置しておりますので、「どのような分煙を行えばよいのかわからない!」「現状の喫煙に関する課題を解決したい!」などのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
それぞれにあった、分煙方法をご提案いたします。
まとめ
喫煙に関する法律改正では、大きな変化がありました。
その変化とは、受動喫煙防止がマナーからルール化されたことです。
また、違反した場合には罰則が適用される場合もあり、違反した内容によって異なりますが、50万円以下の過料となる場合もあります。
そのため、企業ではしっかりとした受動喫煙防止対策を行うことが大切です。
さらに、配慮義務ついても理解しておく必要があります。