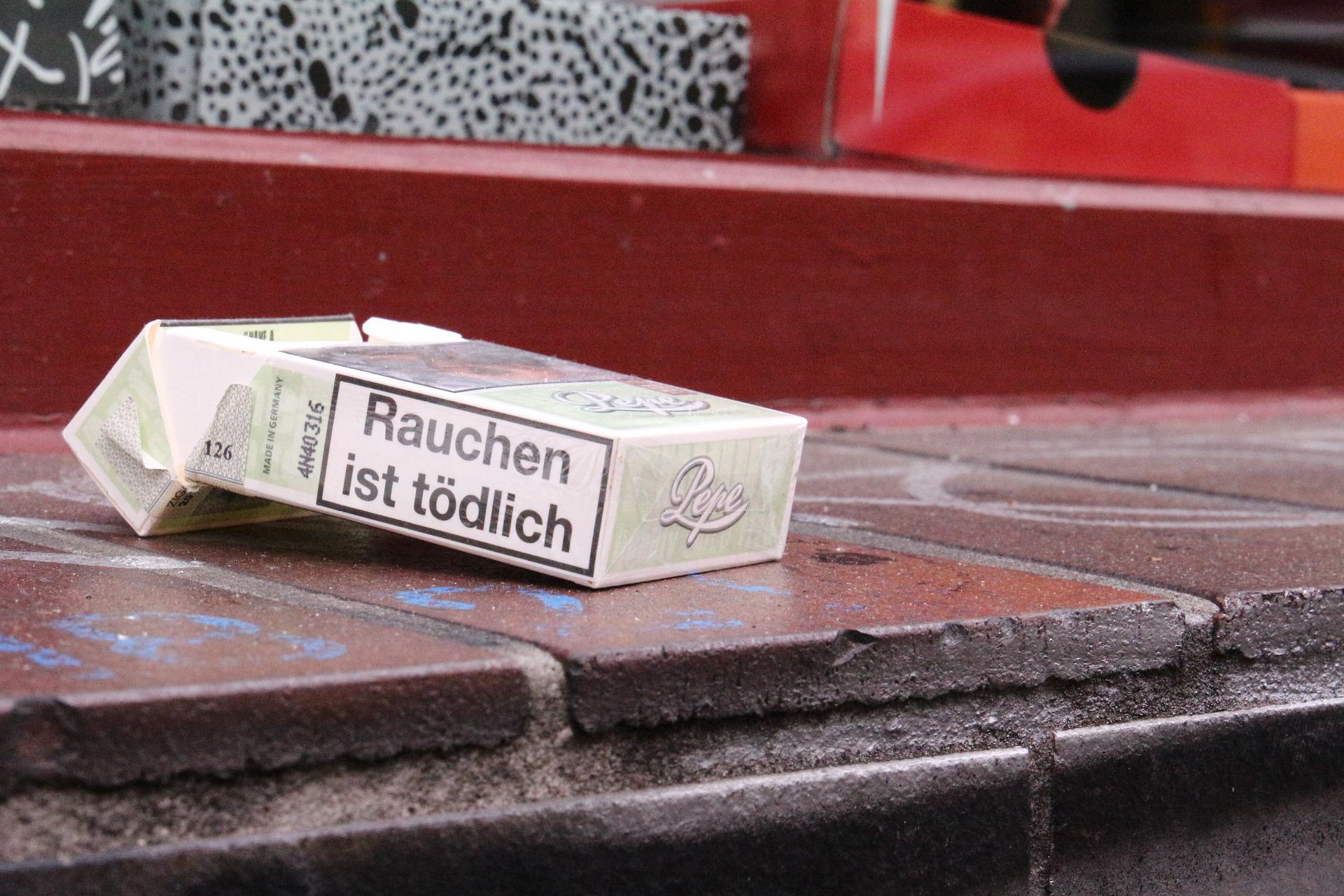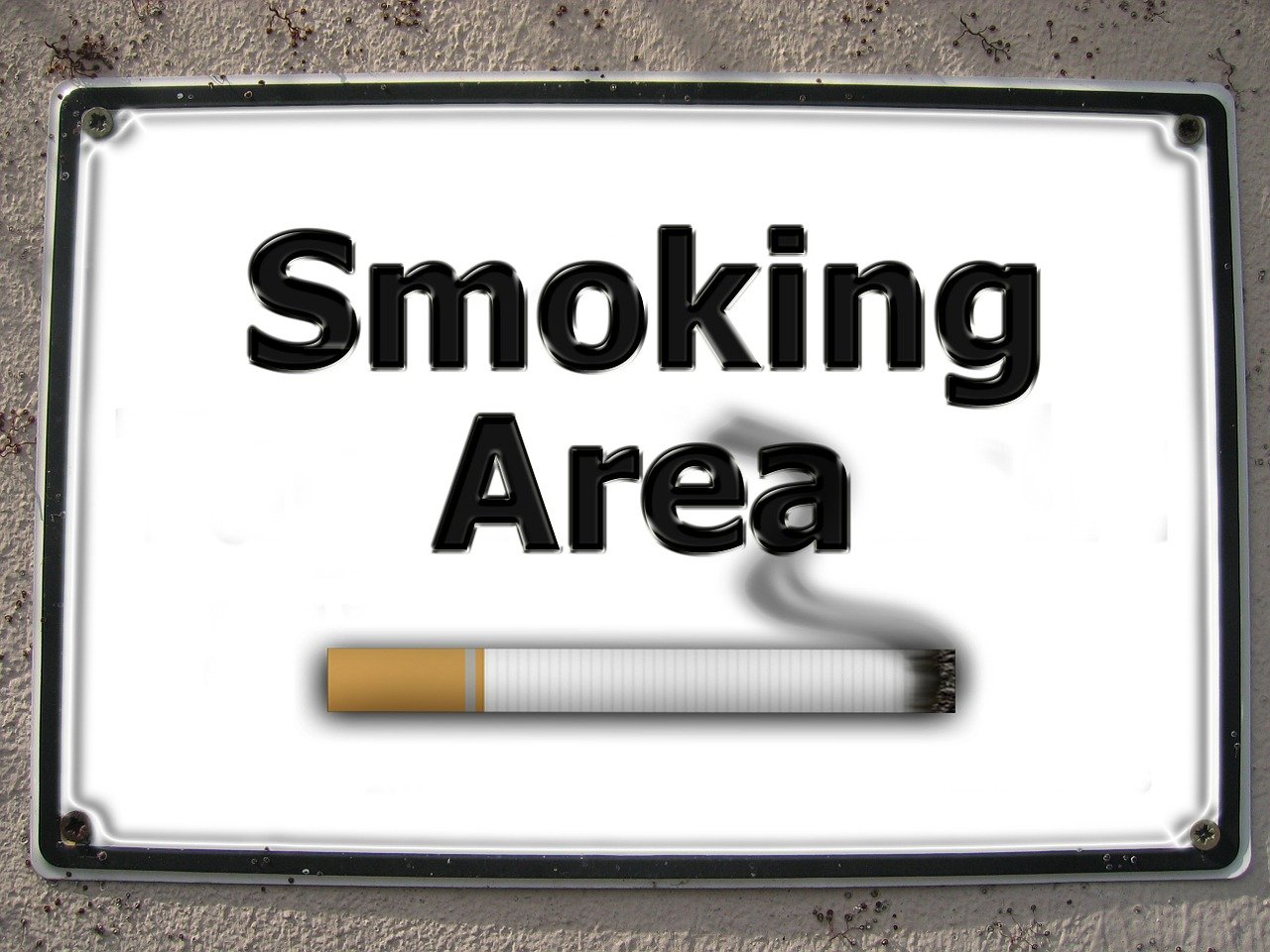2022.09.07
喫煙所コラム
会社の喫煙所ではルールとマナーを守ることで共存が可能!

職場や施設では、喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
望まない受動喫煙を防止するのはもちろんですが、その他にも両者が共存するために、重要なポイントがあります。
今回のコラムでは、そのポイントについて見ていきましょう。
受動喫煙とは
一般的に、職場や施設など多くの人が集まる場所では、喫煙者と非喫煙者が混在しています。
両者の共存を考えるには、まず「受動喫煙とは何か?」について正しく理解する必要があるでしょう。
簡単に解説すると、受動喫煙とは自分が喫煙をしていなくても、周囲のたばこの煙を吸わされてしまうことです。
つまり、自分の意志に関わらず、喫煙しているのと同じような状態になってしまいます。
また、副流煙には多くの有害物質が含まれており、受動喫煙による健康への影響が懸念されているのです。
具体的な健康リスクとしては、肺がん・心筋梗塞・脳卒中・狭心症などのリスクが高まると言われています。
自分は、喫煙をしていないから大丈夫と思っていても、家庭や職場などで周囲に喫煙者がいると、受動喫煙のリスクがあるということを理解しなければなりません。
受動喫煙防止のルールを徹底することが重要
喫煙者だけでなく、非喫煙者の健康にも大きな影響を及ぼす可能性があるため、受動喫煙防止のルールを徹底することが重要です。
施設の種類によって、喫煙に関するルールが異なる場合もありますが、まずは喫煙ルールをしっかりと確認して、望まない受動喫煙を防止することが大切となります。
望まない受動喫煙を防止するためには、次のようなルールを徹底することが必要です。
○ 喫煙可能な場所と喫煙できない場所を明確にすること
○ 喫煙可能な場所以外での喫煙を認めないこと
○ 清掃をしっかりと定期的に行うこと
○ 屋外に設置する場合も周囲の状況に注意して、十分な配慮を行うこと
マナーの3Point((1)Place(場所) (2)People(人々) (3)Poisute(ポイ捨て))
マナーの向上という点で押さえておかなければならないのが、3つのポイントです。
①Place(場所)
マナーの向上で必ず押さえておかなければいけないのが、Place(場所)。
おそらく多くの喫煙者は、屋外であれば、あるいは自宅であれば自由に喫煙が可能であると考えていることでしょう。
もちろん、場所によっては規制の対象外となっている場所もあるのですが、規制の対象外となっている場所でも配慮義務があります。
ですから、喫煙をする場合には必ず場所を意識するようにしましょう。
人通りの多い場所や子ども等がいる場所、隣接する人家があるような場所などでは、喫煙をすると、受動喫煙の可能性があります。
たばこの煙は、喫煙者が想像しているよりもずっと遠くまで届くため、場所を考えて喫煙をしないと、大きなトラブルに発展する可能性があるのです。
②People(人々)
それから、最初に解説したように受動喫煙によって、喫煙者だけでなく、非喫煙者の健康に大きな悪影響を及ぼす可能性があるということを理解しなければなりません。
たばこの煙は、喫煙者以外にも影響があると理解していれば、周囲の人に意識をして、望まない受動喫煙を防止することができます。
喫煙できればよい、規制の対象外だから喫煙をしてもよいということではなく、マナーの向上に努めましょう。
とくに、トラブルになりやすいのが自宅のベランダや庭での喫煙です。
マンションのベランダで喫煙をすると、風に乗ってたばこの煙が周囲の部屋に届いてしまいます。
そのため、たばこをめぐって大きなトラブルに発展してしまうケースがあるのです。
実際に管理会社にクレームが入ることや他の住民から喫煙を注意されてしまうケースもあります。
さらに、最悪の場合には訴訟に発展してしまうケースもあるようです。
訴訟を起こされてしまうと、金銭的な面でも大きな負担となりますし、その後も住み続けるのが難しくなってしまうこともあります。
ですから、トラブルなどに発展してしまうのを防ぐためにも、他の人々に十分な配慮を行うことを忘れないようにしましょう。
③Poisute(ポイ捨て)
たばこをめぐるトラブルで多くなっているのが、吸い殻のポイ捨てです。
灰皿が設置されている場所もありますが、灰皿が設置されていないケースもあります。
灰皿が設置されていないからといって、吸い殻をポイ捨てしていませんか?
喫煙者はポイ捨てすることに、何も感じないかもしれません。
しかし、吸い殻をポイ捨てした場合、次のような問題が起こるのです。
○ 火災発生のリスク
○ 清掃の負担が大きくなる
○ 環境汚染につながるリスク
たばこの吸い殻をポイ捨てした場合、最も懸念されるのが火災。
火のついたままの吸い殻をポイ捨てすると、それが周囲に広がり火災発生のリスクが高まります。
実際に、たばこの吸い殻のポイ捨てによって火災が起きた例も多くあるのです。
その他で大きな問題となるのが、清掃の負担が大きくなってしまうということ。
たばこの吸い殻がポイ捨てされている光景を目にしますが、その吸い殻を清掃しているのは周囲の住民やボランティアの人というケースが多くなっています。
多くの人が吸い殻をポイ捨てすると、清掃を頻繁に行わなければならず、また吸い殻を回収するまでの時間も長く必要となるため、負担が大きくなってしまうでしょう。
さらに、覚えておかなければならないのが、吸い殻をポイ捨てすることによって、環境汚染につながる可能性があるということです。
すでに解説しましたが、たばこには多くの有害物質が含まれています。
そのようなたばこの吸い殻をポイ捨てした場合、その吸い殻から有害物質が染み出してしまい、周囲の環境を汚染してしまう可能性があるのです。
環境汚染につながってしまえば、もとの状態に戻すのが困難となってしまいますし、人間だけでなく動物など他の生態系にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このような理由からも、たばこの吸い殻はポイ捨てするのではなく、喫煙者が責任を持って片付けることが大切です。
喫煙マナーの向上のためにも、たばこの吸い殻をポイ捨てするのではなく、携帯灰皿を持つという習慣を持つとよいでしょう。
最近では小型の携帯灰皿も多く販売されていますので、灰皿がない場所でも吸い殻の処分に困らないように携帯灰皿を準備するのがおすすめです。
マナーの向上が共存を可能にする
喫煙者と非喫煙者の共存を可能にするためには、喫煙ルールをしっかりと守るのはもちろんですが、マナーの向上が不可欠となります。
とくに、非喫煙者の多くはたばこの煙、臭いが苦手なので、十分な配慮が求められるでしょう。
たばこの煙や臭いが苦手という人への配慮として、脱臭機などを設置するのも効果的です。
もちろん、完全に除去できるというわけではありませんが、設置することで臭いの軽減に役立ちます。
反対に、十分な配慮を行わなければ、喫煙者と非喫煙者が共存するのが難しくなってしまうでしょう。
まとめ
喫煙者と非喫煙者が混在しているのが一般的です。
両者が共存するためには、望まない受動喫煙を防止するのはもちろんですが、喫煙マナーを向上させることも非常に重要となります。
反対に喫煙ルールを守らない、あるいは喫煙マナーが悪いということでは、両者の共存は難しくなってしまうでしょう。
共存するためには、喫煙マナーの向上が不可欠です。